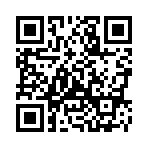› マロンの冒険 › みよしみあわせ
› マロンの冒険 › みよしみあわせ2009年07月16日
みよしみあわせ
火曜日の朝には、豊島の海苔の漁師の大西さん(Oさん)に船を出してもらって、小豊島の船大工さんを尋ねました。(あとでわかったのですが、Oさんの奥さんは小豊島のご出身だったので、大工さんと心安かったから紹介を引き受けてくれたんだそうです)
豊島の人の物事の始め方には、あらかじめ電話でアポなどは取らないで、まずはいきなり訪ねていって、お家に目当ての人がいたらそこから話を始める・・という方法が多いです(私の知る限りでは)。
こうすることによって無駄足も多いけどお話を始めたり、約束したりするには、もっとも確実な方法で、相手の都合も顔色や空気で感じることができる良い方法なのかもしれないと思いました。(よく考えたら、アポを取るということは、その時間は私のために空けておいてね。と相手を拘束することでもあるのですね)
よって、マロンの「船大工さん初訪問&インタビュー」についても、その方式に則って行われました。
要するにアポなし。。。
9時40分 オープンカー(軽トラ)で唐櫃漁港到着。
待機していてくれたOさんの漁船に乗り込んで小豊島へ向けて出港します。

この日はめちゃくちゃ暑かったのですが、快い速度で走る漁船の上は涼しくて別世界です。

豊島から小豊島の海峡には、船の免許教室で習った「洗岩」とか「暗岩」がちらほら。。
当然のことながらOさんの頭には海図がしっかり入っているので、難なく通り抜けます。

10分も走らないうちに小豊島に到着しました。
豊島もマロンにとってはとても非日常なところですが、小豊島はもう一段深い異国でした。
静かな静かな漁港から見上げると緑の濃い山。
この島は人が10数名しか住んでいないのですが、山の向こうの牧場には肉牛が450頭いるそうです。島に上がってすぐのところに、「畜魂碑」と書かれた石がひっそりとあります。
小豊島の船大工さんの竹内さんのお家は漁港に面したところにありました。
船伝いに桟橋にあがって、「大工さんおるかなあ」と話しながら歩いていたら、偶然にも向こうから竹内さんが歩いてこられました。Oさんが必要にして最小限の言葉でマロンを紹介してくれます。
竹内さんは、突然の訪問なのに、嫌な顔ひとつせず、涼しい木陰に縁台を出してきてくれて「ここに座りんせい」と、台を進めてくれました。
10代の頃からお父さんの後を次いで和船を作っていて、現在85歳。

少しお耳は遠いのですが、しっかりと船のお話をしてくださいました。
新造の船を作る行程は、「四尋の伝馬船で7日」と決まっているそうです。(一尋は人間が両手をいっぱいに広げた長さ)
1日目は、かわらと呼ばれる船の底を作り
2日目〜5日目は外板を作り、つけ
6日目〜7日目にトダテ(魚を入れる船の中の池)をつける
材料は、べんこうと呼ばれる九州の杉が最も適しているのだそうです。
豊島の杉は柔らかめで水が沁みやすいから向かないんだとか。
「なにか設計図のようなものはあるのですか?」と訪ねたら、奥から古い板に墨で、船を横から見た図を描いたものを持ってきてくれました。
昭和37年 高島さんという方のために作った船で、材料は小豊島の松の木だったそうです。

教えてほしかったことのひとつに、閼伽(水)止めに、船板の隙間に差し込む材料は、楠の皮なのかどうかということでした。
答えは、楠ではなく、桧の、それも外ではなく内側の柔らかい皮を紐状にしたものでした。
これも作業場の奥から持ってきて見せてくれました。(帰りには、一束を持たせてくださいました)

鐫を使って、このように閼伽を止めるんだそうです。

これは、竹内さんが20歳くらいの頃、大木を船用に製材するときに使っていた大鋸。

これは炭壷。

次に、竹内さんは船霊さんの話をしてくれました。
「どんな船にも、船には神さんが乗っておるんじゃ。ふなだまさんというてな。」
そして、作業場の奥からなんとその実物を持って来て見せてくれたのです。
こればかりは写真を撮ったらいけない気がして画像がありませんが、船霊さんはやはり桧で出来ていて、巨大な将棋の駒みたいな五角形をしています。
よく見ると木のお腹のところに切れ目があって、相似形に小さい五角形の蓋がぴったりとはめられていました。
「このなかには、いろいろと入れるもんがあるんじゃ」
ひとつは、13円(貨幣価値の変化とともに円になったようですが)。理由はひと月1円で一年間守っていただくのですが、閏年があるので、13円入れるのだそうです。
そしてもうひとつ、「船霊さんのご神体はこれなんじゃ」
と言って、竹内さんが見せてくれたものは、「えっ!!」と驚くようなものでした。
ご神体の意味は
「いってんいちろく みよしみあわせ ともにしあわせ」 で、
「波や風が強い時は無理をするな。無理をしなければ家族やまわりがともにしあわせになるから。」
ということだそうです。
こちらは、舵や櫂まで丁寧に作られた精霊船です。

もう一つ不思議でびっくりしたことは、ヨットの話など一度もしていないのに、さきほど見せてくれた「船霊さん」を私に差し出して、『これを持っていきんせ。あんたの船に乗せんせ』と、くださったことです。
あまりのことに、言葉が見つからず、「ありがとうございます」しか言えなくなっている自分がいました。
竹内さんはお酒を飲まれないということ以外、お好みがわからないので、今回は気持ちばかりの笹団子を提げていったのですが、帰り際には真顔で「もう今度は何も持ってこんでええ。あんまり気を使うんやったら、もう来れんで!」と言われてしまいました。
どこの馬の骨かもわからないマロンを、いくら知っている人からの紹介とはいえ快く迎えてくださって、「そんなことまで教えてもらっていいのですか?」というほどいろんな話をしてくれた竹内さん。
何十年も和船を作り続けた人はこんな顔と目になるんだ」と感動せずにはいられないような綺麗な竹内さんを見ていたら、悲しい話などひとつもなさらなかったのに、時折目がうるうるしてくるのでした。
いつか、近いうちに、ここにみんなを連れて来て、和船の作り方を教えてもらったり、小さな灯籠船を作らせてもらいたい。できれば人が乗れて走れる船をつくりたい。そして、できる限りのことを後の人に伝達する手伝いがしたい。
これまでにこんな挨拶で人と別れたことはないのですが、
「またこの夏のうちにもう一回来てもいいですか? それまでどうかお元気でいてくださいね」という言葉が口をついて出てしまいました。
この訪問は、きっとずっと忘れることのできない心に残る光景になりました。
Oさん(←マロンが大ファンになってしまった漁師さんです)、本当に本当にありがとうございました(Oさんがこのブログを見ることは絶対にないと思われますが、お礼を言わせてください)。
豊島の人の物事の始め方には、あらかじめ電話でアポなどは取らないで、まずはいきなり訪ねていって、お家に目当ての人がいたらそこから話を始める・・という方法が多いです(私の知る限りでは)。
こうすることによって無駄足も多いけどお話を始めたり、約束したりするには、もっとも確実な方法で、相手の都合も顔色や空気で感じることができる良い方法なのかもしれないと思いました。(よく考えたら、アポを取るということは、その時間は私のために空けておいてね。と相手を拘束することでもあるのですね)
よって、マロンの「船大工さん初訪問&インタビュー」についても、その方式に則って行われました。
要するにアポなし。。。
9時40分 オープンカー(軽トラ)で唐櫃漁港到着。
待機していてくれたOさんの漁船に乗り込んで小豊島へ向けて出港します。

この日はめちゃくちゃ暑かったのですが、快い速度で走る漁船の上は涼しくて別世界です。

豊島から小豊島の海峡には、船の免許教室で習った「洗岩」とか「暗岩」がちらほら。。
当然のことながらOさんの頭には海図がしっかり入っているので、難なく通り抜けます。

10分も走らないうちに小豊島に到着しました。
豊島もマロンにとってはとても非日常なところですが、小豊島はもう一段深い異国でした。
静かな静かな漁港から見上げると緑の濃い山。
この島は人が10数名しか住んでいないのですが、山の向こうの牧場には肉牛が450頭いるそうです。島に上がってすぐのところに、「畜魂碑」と書かれた石がひっそりとあります。
小豊島の船大工さんの竹内さんのお家は漁港に面したところにありました。
船伝いに桟橋にあがって、「大工さんおるかなあ」と話しながら歩いていたら、偶然にも向こうから竹内さんが歩いてこられました。Oさんが必要にして最小限の言葉でマロンを紹介してくれます。
竹内さんは、突然の訪問なのに、嫌な顔ひとつせず、涼しい木陰に縁台を出してきてくれて「ここに座りんせい」と、台を進めてくれました。
10代の頃からお父さんの後を次いで和船を作っていて、現在85歳。

少しお耳は遠いのですが、しっかりと船のお話をしてくださいました。
新造の船を作る行程は、「四尋の伝馬船で7日」と決まっているそうです。(一尋は人間が両手をいっぱいに広げた長さ)
1日目は、かわらと呼ばれる船の底を作り
2日目〜5日目は外板を作り、つけ
6日目〜7日目にトダテ(魚を入れる船の中の池)をつける
材料は、べんこうと呼ばれる九州の杉が最も適しているのだそうです。
豊島の杉は柔らかめで水が沁みやすいから向かないんだとか。
「なにか設計図のようなものはあるのですか?」と訪ねたら、奥から古い板に墨で、船を横から見た図を描いたものを持ってきてくれました。
昭和37年 高島さんという方のために作った船で、材料は小豊島の松の木だったそうです。

教えてほしかったことのひとつに、閼伽(水)止めに、船板の隙間に差し込む材料は、楠の皮なのかどうかということでした。
答えは、楠ではなく、桧の、それも外ではなく内側の柔らかい皮を紐状にしたものでした。
これも作業場の奥から持ってきて見せてくれました。(帰りには、一束を持たせてくださいました)

鐫を使って、このように閼伽を止めるんだそうです。

これは、竹内さんが20歳くらいの頃、大木を船用に製材するときに使っていた大鋸。

これは炭壷。

次に、竹内さんは船霊さんの話をしてくれました。
「どんな船にも、船には神さんが乗っておるんじゃ。ふなだまさんというてな。」
そして、作業場の奥からなんとその実物を持って来て見せてくれたのです。
こればかりは写真を撮ったらいけない気がして画像がありませんが、船霊さんはやはり桧で出来ていて、巨大な将棋の駒みたいな五角形をしています。
よく見ると木のお腹のところに切れ目があって、相似形に小さい五角形の蓋がぴったりとはめられていました。
「このなかには、いろいろと入れるもんがあるんじゃ」
ひとつは、13円(貨幣価値の変化とともに円になったようですが)。理由はひと月1円で一年間守っていただくのですが、閏年があるので、13円入れるのだそうです。
そしてもうひとつ、「船霊さんのご神体はこれなんじゃ」
と言って、竹内さんが見せてくれたものは、「えっ!!」と驚くようなものでした。
ご神体の意味は
「いってんいちろく みよしみあわせ ともにしあわせ」 で、
「波や風が強い時は無理をするな。無理をしなければ家族やまわりがともにしあわせになるから。」
ということだそうです。
こちらは、舵や櫂まで丁寧に作られた精霊船です。

もう一つ不思議でびっくりしたことは、ヨットの話など一度もしていないのに、さきほど見せてくれた「船霊さん」を私に差し出して、『これを持っていきんせ。あんたの船に乗せんせ』と、くださったことです。
あまりのことに、言葉が見つからず、「ありがとうございます」しか言えなくなっている自分がいました。
竹内さんはお酒を飲まれないということ以外、お好みがわからないので、今回は気持ちばかりの笹団子を提げていったのですが、帰り際には真顔で「もう今度は何も持ってこんでええ。あんまり気を使うんやったら、もう来れんで!」と言われてしまいました。
どこの馬の骨かもわからないマロンを、いくら知っている人からの紹介とはいえ快く迎えてくださって、「そんなことまで教えてもらっていいのですか?」というほどいろんな話をしてくれた竹内さん。
何十年も和船を作り続けた人はこんな顔と目になるんだ」と感動せずにはいられないような綺麗な竹内さんを見ていたら、悲しい話などひとつもなさらなかったのに、時折目がうるうるしてくるのでした。
いつか、近いうちに、ここにみんなを連れて来て、和船の作り方を教えてもらったり、小さな灯籠船を作らせてもらいたい。できれば人が乗れて走れる船をつくりたい。そして、できる限りのことを後の人に伝達する手伝いがしたい。
これまでにこんな挨拶で人と別れたことはないのですが、
「またこの夏のうちにもう一回来てもいいですか? それまでどうかお元気でいてくださいね」という言葉が口をついて出てしまいました。
この訪問は、きっとずっと忘れることのできない心に残る光景になりました。
Oさん(←マロンが大ファンになってしまった漁師さんです)、本当に本当にありがとうございました(Oさんがこのブログを見ることは絶対にないと思われますが、お礼を言わせてください)。