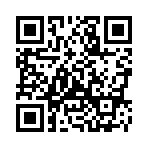› マロンの冒険 › 連歌
› マロンの冒険 › 連歌2009年08月16日
こんなんあります。
今週水曜日のお誘いです。
今日中のお申し込みで、あと3名様まで受付可能です。
連歌の面白さは、ちょっと頑張って書いたこちらをご覧下さい★
***************************
高城修三連歌講座 葉月の半歌仙 へのお誘い
謹啓
お盆も過ぎ、朝夕しのぎやすくなって参りました。
さて、来月、女木島にて半歌仙の連歌会を開催いたしたく、下記のとおりご案内申し上げます。
今回は、高松の料亭二蝶さんの新築されたばかりの別荘をお借りすることができました。
ゆっくりと島時間を味わいながら、江戸末期で一旦封印させられた連歌の復興に血道を上げる芥川賞作家高城修三宗匠の熱い指導の許、場が作る文学である連歌を存分に味わっていただきたく存じておりますので、ふるってご臨席を賜りますよう、お願いいたします。
敬白
記
日 時:2009年8月19日(水)午後12時30分〜16時30分
(12時30分〜13時30分まではお弁当を召し上がっていただき、その後、
13時30分より連歌会を開始する予定です)
会 場:女木徳永邸(高松市女木町)
集合場所:女木島行きフェリー乗り場(県営第一桟橋)
集合時間:11時50分
※他の方法やそれ以前の時間に女木島入りされる方はお知らせください。
会 費:6,000円(宗匠謝礼+往復船賃+お弁当+飲み物代として)
出欠連絡先:事務局マロンまで、メッセージかコメントでお知らせください。
※高松行き帰りの便へは、17時、または18時10分女木島発に乗船予定です。
今日中のお申し込みで、あと3名様まで受付可能です。
連歌の面白さは、ちょっと頑張って書いたこちらをご覧下さい★
***************************
高城修三連歌講座 葉月の半歌仙 へのお誘い
謹啓
お盆も過ぎ、朝夕しのぎやすくなって参りました。
さて、来月、女木島にて半歌仙の連歌会を開催いたしたく、下記のとおりご案内申し上げます。
今回は、高松の料亭二蝶さんの新築されたばかりの別荘をお借りすることができました。
ゆっくりと島時間を味わいながら、江戸末期で一旦封印させられた連歌の復興に血道を上げる芥川賞作家高城修三宗匠の熱い指導の許、場が作る文学である連歌を存分に味わっていただきたく存じておりますので、ふるってご臨席を賜りますよう、お願いいたします。
敬白
記
日 時:2009年8月19日(水)午後12時30分〜16時30分
(12時30分〜13時30分まではお弁当を召し上がっていただき、その後、
13時30分より連歌会を開始する予定です)
会 場:女木徳永邸(高松市女木町)
集合場所:女木島行きフェリー乗り場(県営第一桟橋)
集合時間:11時50分
※他の方法やそれ以前の時間に女木島入りされる方はお知らせください。
会 費:6,000円(宗匠謝礼+往復船賃+お弁当+飲み物代として)
出欠連絡先:事務局マロンまで、メッセージかコメントでお知らせください。
※高松行き帰りの便へは、17時、または18時10分女木島発に乗船予定です。
2009年06月17日
中間報告
本日は午後から連歌と女神と庵治な一日を送っておりました。
連歌講座後半の部恒例の「月をまたいで半歌仙を巻こうシリーズ」では、高城先生の指導のもと、3月から1句〜2句ずつ作り進め、本日でようやく6句め(裏初句)まで辿りつきました。
本日までの興行結果は次のとおり
表発句 ビークルが香り鳴きして谷深し
脇 雪の降る中我はただ耳
第三 空中に止まりしリフトまたゆれて
第四 足下にあじさい四国三郎
第五 弘法の丹を求めて幾星霜
第六 月光さんさん骨を照らして
裏初句 秋祭り鐘も太鼓も華やいで
来月(7月)はこの次(裏二句)からです。
そろそろ恋の句が出てもいい頃かな、なんて話も出ました。
ちなみにマロンは来月はこんな句を孕んで行こうかと思ってます。
候補1 マンハッタンのチャイナタウンは
候補2 鳥居の脇で 落ち合う予定
みなさんならどんな7.7をつけますか?
芥川賞作家高城修三先生の直伝「連歌講座」。来月は15日の午後2時から、番町中條財団にて。
講座終了後は、可憐なH会長につかまって、豊島バーのやり方等についていろいろとご指導を賜っておりました。途中話が脱線して、屋島だぬきの日露戦争での活躍についてもお教えいただき、おもしろいのなんのって♪
なんでも、えべっさんのま隣のお家が借りられたこと自体が奇跡だそうです。船と音楽と芸能の神様に招かれたわけだから、せっかくなら一流の建築家に店の本格改装を依頼して、おえべっさんのお祭り会場に相応しい設えが必要とのことです。さて、実現するかな?
そして本日夕方からは、今秋初開催の野外カクテルパーティーの打ち合わせに「森三」まで参じておりました。
なぜかマロンが催事名称を考える担当者に、光栄にも任命していただきまして、あれこれ考えたけれど出てきた案は2つ、そのうちメンバーに承認いただいたのは以下の名前です。(Diossaはスペイン語で「女神」)
Fes Diossa 〜カクテルガーデン〜
実行委員会のメンバーは若くしてエグゼクティブな風情漂う方がちらほら。。
実行委員長は女神のお祭りに相応しい才色兼備なシニアソムリエ。
これまで一緒に活動したことある人は、声掛け人のT氏だけ(多分)なので、適度にアウェイな解放感を楽しんでおります。
舌とお腹と目の保養ができる内容になりそうですよ!
そして本日最後は、愛する盟友とともに、庵治の主の誘導で、とある物件を数個所物色に行っておりました。
久しぶりの庵治、少しの時間でしたが、相変わらず素敵なところだと実感いたしました。
今日もありがとう。
連歌講座後半の部恒例の「月をまたいで半歌仙を巻こうシリーズ」では、高城先生の指導のもと、3月から1句〜2句ずつ作り進め、本日でようやく6句め(裏初句)まで辿りつきました。
本日までの興行結果は次のとおり
表発句 ビークルが香り鳴きして谷深し
脇 雪の降る中我はただ耳
第三 空中に止まりしリフトまたゆれて
第四 足下にあじさい四国三郎
第五 弘法の丹を求めて幾星霜
第六 月光さんさん骨を照らして
裏初句 秋祭り鐘も太鼓も華やいで
来月(7月)はこの次(裏二句)からです。
そろそろ恋の句が出てもいい頃かな、なんて話も出ました。
ちなみにマロンは来月はこんな句を孕んで行こうかと思ってます。
候補1 マンハッタンのチャイナタウンは
候補2 鳥居の脇で 落ち合う予定
みなさんならどんな7.7をつけますか?
芥川賞作家高城修三先生の直伝「連歌講座」。来月は15日の午後2時から、番町中條財団にて。
講座終了後は、可憐なH会長につかまって、豊島バーのやり方等についていろいろとご指導を賜っておりました。途中話が脱線して、屋島だぬきの日露戦争での活躍についてもお教えいただき、おもしろいのなんのって♪
なんでも、えべっさんのま隣のお家が借りられたこと自体が奇跡だそうです。船と音楽と芸能の神様に招かれたわけだから、せっかくなら一流の建築家に店の本格改装を依頼して、おえべっさんのお祭り会場に相応しい設えが必要とのことです。さて、実現するかな?
そして本日夕方からは、今秋初開催の野外カクテルパーティーの打ち合わせに「森三」まで参じておりました。
なぜかマロンが催事名称を考える担当者に、光栄にも任命していただきまして、あれこれ考えたけれど出てきた案は2つ、そのうちメンバーに承認いただいたのは以下の名前です。(Diossaはスペイン語で「女神」)
Fes Diossa 〜カクテルガーデン〜
実行委員会のメンバーは若くしてエグゼクティブな風情漂う方がちらほら。。
実行委員長は女神のお祭りに相応しい才色兼備なシニアソムリエ。
これまで一緒に活動したことある人は、声掛け人のT氏だけ(多分)なので、適度にアウェイな解放感を楽しんでおります。
舌とお腹と目の保養ができる内容になりそうですよ!
そして本日最後は、愛する盟友とともに、庵治の主の誘導で、とある物件を数個所物色に行っておりました。
久しぶりの庵治、少しの時間でしたが、相変わらず素敵なところだと実感いたしました。
今日もありがとう。
2009年01月23日
ジョニーさんの発句

ひさしぶりにウダウダな午後、立ちはだかるtodoを見ないふりして・・・連歌の話です
(けいぴょんの質問にもお答えできる形になればいいなと。。)
1月の「高城修三の連歌講座」では、初参加の方のために、
■前半は連歌とは何かと、
■その成り立ちや変遷、
■台頭した歴史上の人物(芭蕉は俳句の人ではなく、連歌師であったこと等)、
■連歌のルール
をささっとおさらいしましたが、後半では、実際に連歌を作ってみるスタイルの講義がなされました。
とは行っても、実践ではないので、発句なら発句、脇なら脇と、できた人が手を挙げてすぐに採否は決めずに板書していき、出尽くしたところで、一つ一つの分析研究をして最後に本日の採択句を決めるという流れで進められました。
まずは発句です。
発句のルールは、
1. 季語が入っていることと、
2. 切れ字が入っていることで(かな、けりetc)
3. 575であることです。
季語は今の季節は旧暦新暦太陽暦太陰暦によって、春であったり冬であったり、新年であったりするので、あまり複雑に考えずに、読む人が「冬」なら『冬」で決めて作ればよいわけです。
今回教場で出そろった句は
★ 雪止んで 香立ちこめる 庵かな
★ ビーグルが香り鳴きして谷深し
★ 蕗の薹 育む雨と なりにけり
★ 野良犬も 背中丸めて ○○○○○(←忘れました・汗)
の四句でしたが、高城先生が選んだ句は
ビーグル・・の句、初参加のジョニーさんの作った句です。
この場合「香り鳴き」(←猟犬がイノシシの匂いを察知した時に鳴くことをいうそうで、冬の季語)が先生にとっても新しい言葉で新鮮なので、、ということで採用されました(さすがジョニーさんです)
で、
2月は、これに脇をつけるところから始まります。
脇のルールは、
1. 体言止め(名詞止め)、
2. 季語は発句と同じにする、
3. 77で作る といった所です。
これが、すぐに決まれば第三、第四と続きます。
次に受講してくださる方は、この脇を作って行ってもいいそうです。(作らなくてもいい)
(実際の連歌では、予め句を作って会場入りすることを「孕み句」と呼び、禁止条項に入っています)
てことで、
いろんな意味でエキサイティングな講座になることは保証いたしますので、是非是非是非来てね♪>けいぴょん、ご興味と時間のあるすべての方
2008年12月23日
デビュー
去る12月17日には、内町の鍋料理店「度々」で、今年最後の連歌会が開催されました。
いつものメンバーに加え、「マロンの冒険」最多出場と思われるマナベヒデタカ氏と、ノーマライゼーションの実践者「御意」のホソカワマナブ氏に初参加いただきました。
並み居るベテラン強豪の中、連歌デビューほやほやマナベ氏がなんと「花の定座」で自句を採択されました。
興行結果は以下のとおり。
http://www.h2.dion.ne.jp/~taki99/seishoutei.htm
松尾芭蕉も何度も強調しているのは、「連歌を面白くするのは普段連歌とはまったく違う世界で生きている人の参加である」ということが実感された良い会でした。
みなさまも是非〜

いつものメンバーに加え、「マロンの冒険」最多出場と思われるマナベヒデタカ氏と、ノーマライゼーションの実践者「御意」のホソカワマナブ氏に初参加いただきました。
並み居るベテラン強豪の中、連歌デビューほやほやマナベ氏がなんと「花の定座」で自句を採択されました。
興行結果は以下のとおり。
http://www.h2.dion.ne.jp/~taki99/seishoutei.htm
松尾芭蕉も何度も強調しているのは、「連歌を面白くするのは普段連歌とはまったく違う世界で生きている人の参加である」ということが実感された良い会でした。
みなさまも是非〜

2008年11月19日
忘年連歌会のごあんない

さぬき倶楽部連歌講座忘年連歌会
日 時:12月17日(水) 午後3時~午後5時半(連歌会)
午後6時~午後8時(忘年会)
場 所:度々(たびたび)
高松市内町2番19号(三越東館の北東出口の前、元竹林寺というお店でした)
電話087-822-2278
メニュー:旬シャブ&鶏鍋とワインほかお飲物
参加費:8000円
ご興味のある方はどうぞ♪
2008年08月23日
国際手配の君追いかけて
先週水曜日に行われた連歌会の興行結果をご報告します。
お天気がどうなるか心配でしたが,時折強すぎるくらいの涼風の中,カレントスタイル(瀬戸内ベースソトメシ担当)の大岡さんが腕を振るってくれた冷製パスタ,カルパッチョ,タコのマリネとワイン三昧の中,素敵な18句が揃いました♪
来月からは,心機一転初心者の方の入門しやすい講座を始めることになりそうです。(9月17日午後
この機会にみなさまも,是非「近代に封印された日本文学である連歌」を紐解く仲間になってくださいませ。
http://www.h2.dion.ne.jp/~taki99/seishoutei.htm
)
お天気がどうなるか心配でしたが,時折強すぎるくらいの涼風の中,カレントスタイル(瀬戸内ベースソトメシ担当)の大岡さんが腕を振るってくれた冷製パスタ,カルパッチョ,タコのマリネとワイン三昧の中,素敵な18句が揃いました♪
来月からは,心機一転初心者の方の入門しやすい講座を始めることになりそうです。(9月17日午後
この機会にみなさまも,是非「近代に封印された日本文学である連歌」を紐解く仲間になってくださいませ。
http://www.h2.dion.ne.jp/~taki99/seishoutei.htm
)

2008年05月21日
本日午後から番町へ
中條財団にて、連歌講座がございます。
高城修三先生(芥川賞受賞作家)が講師で、座学&抹茶。
午後3時から、飛び入りでもなんとかなりますので、よろしければ是非お越しください。
授業料は3000円。
明日は午前中に肥土山の保存会会長に法被を返すためにお目にかかります。
10.45にumieで、というお約束ながら11時15分には出なくてはならない旨を告げると
「あら、そしたらお茶飲めないんじゃないか? 小腹が空くけどだいじょうぶ?」
と心配されてしまいました。
私のコバラの存在が、局地的に人に知られる事になっている気配。。

高城修三先生(芥川賞受賞作家)が講師で、座学&抹茶。
午後3時から、飛び入りでもなんとかなりますので、よろしければ是非お越しください。
授業料は3000円。
明日は午前中に肥土山の保存会会長に法被を返すためにお目にかかります。
10.45にumieで、というお約束ながら11時15分には出なくてはならない旨を告げると
「あら、そしたらお茶飲めないんじゃないか? 小腹が空くけどだいじょうぶ?」
と心配されてしまいました。
私のコバラの存在が、局地的に人に知られる事になっている気配。。
2008年04月16日
半歌仙の興行結果
本日の連歌会@晴松亭。
参加者は13人。空いたワインは5本。。
オードブルはガチョウのペースト、イベリコ豚のペースト、カマンベール、オリーブのガーリック漬けetc..
明るいうちからほろ酔いまして、宗匠もご機嫌で調子よく満尾となりました。
興行結果は次のとおりです。
この中のマロンの作った句はどれどれでしょうか!
平成20年4月16日
半歌仙連歌 山つつじ の巻
於 晴松亭
山つづじ鉄橋越しの眺めかな
背伸びしている新入生徒
美しき母の代わりや誰やらむ
寒し寒しと細き白足袋
月の降る渡り廊下をひたひたと
服部半蔵只今参上
ありがたや命からがら浜松へ
酒に浮かれて踊る姫君
汝は知るや千々に乱れる胸の内
竜宮城から離れられない
鯛ヒラメ豊玉姫の美しき
長い立ち読み本屋の隅で
ふりむけばフランス窓に望の月
団子すすきも添えてみようか
こおろぎの清しき声に誘われて
アルゼンチンへ荷造りをする
花嫁はまだ18の乙女なり
永遠の幸せ祈りてやまぬ
※次の連歌会は、4月20日(日)午後1時〜 中野天満宮にて「後藤芝山追善連歌会」 参加費、今度は1000円。ワインは出ませんが、珈琲とケーキがでます♪
参加者は13人。空いたワインは5本。。
オードブルはガチョウのペースト、イベリコ豚のペースト、カマンベール、オリーブのガーリック漬けetc..
明るいうちからほろ酔いまして、宗匠もご機嫌で調子よく満尾となりました。
興行結果は次のとおりです。
この中のマロンの作った句はどれどれでしょうか!
平成20年4月16日
半歌仙連歌 山つつじ の巻
於 晴松亭
山つづじ鉄橋越しの眺めかな
背伸びしている新入生徒
美しき母の代わりや誰やらむ
寒し寒しと細き白足袋
月の降る渡り廊下をひたひたと
服部半蔵只今参上
ありがたや命からがら浜松へ
酒に浮かれて踊る姫君
汝は知るや千々に乱れる胸の内
竜宮城から離れられない
鯛ヒラメ豊玉姫の美しき
長い立ち読み本屋の隅で
ふりむけばフランス窓に望の月
団子すすきも添えてみようか
こおろぎの清しき声に誘われて
アルゼンチンへ荷造りをする
花嫁はまだ18の乙女なり
永遠の幸せ祈りてやまぬ
※次の連歌会は、4月20日(日)午後1時〜 中野天満宮にて「後藤芝山追善連歌会」 参加費、今度は1000円。ワインは出ませんが、珈琲とケーキがでます♪
2008年04月10日
後藤芝山さんを知っていますか?

後藤芝山(ごとう‐しざん)
大辞泉によりますと、
[(一七二一〜一七八二)]江戸中期の儒学者。讚岐(さぬき)の人。
名は世鈞。高松藩主の侍講となり、藩校の講道館を設立。
四書五経に施した訓点は、後藤点として知られる。著「元明史略」など。
とあります。
中学の漢文で習ったレ点などの訓点は、そもそもは後藤芝山が考案し、「後藤点」と呼ばれていたそうです。
現在もその子孫のお一人が高松で会社を経営されています。
来る4月20日に、このさぬきの偉人を追善する連歌会が開催されます。
場所は中野天満宮境内
参加費は1000円なのに、なんと珈琲とケーキがつきます、たぶん。。(←昨年のデータ)
連歌の会は、句が浮かばなければ、他の人の出句を眺めているだけでも楽しい「あそび」です。
こちらは昨年の興行結果です。
http://www.h2.dion.ne.jp/~taki99/sizann.htm
てことで、あなたもあなたも
まだ予定が煮詰まってない方、是非〜♪
記
後藤芝山先生追善連歌会
宗匠:高城修三
午後1時〜午後3時
参加費1000円
お申し込みは18日までにマロンまで!
2008年03月02日
高城修三連歌始め 三句以降

百韻連歌の表8句を詠む。ということで、連歌始めだけは、8句で挙句となります。
小川淳也さんの脇に続いて3句め
雪残る四国の山を下に見る (春はまだまだ遠いんだよと)
三国一の嫁を迎えて (四国から三国へと、、言葉遊びをからめつつ、ズームイン)
青い月愛しき君は人のもの(三国一の嫁を迎えた男には、もう一人恋人がいました)
音無きメール待ちわびる秋(春遠い冬から、場面は一気に秋。メールの音を消して側においておく切ない気持ち。。わかるな)
コスモスの花びら数えとぼとぼと(最後から二句めなので「花」の座。桜は無理なのでコスモス(秋桜)の登場です。
挙句:千年生きたる光源氏よ(とぼとぼ歩いていたのは、千年のプレイボーイでした)
めでたく満尾となりました。
今日の連歌始めでは、農村歌舞伎の宣伝が出来た以外に二つ良い事がありました♪
これまで連歌始めでは、句が採用された試しがなかったのに、今日はすんなり採っていただきました(さて、どの句でしょう?)
もう一つは、名札に付いた番号で、福引きがあったのですが、奈良の陶芸家(出席者の一人)の焼いたお皿が当たりました。
(くじ運は、よくない人生だったので、びっくり)
気がついたら紹興酒でヘロンヘロンのまま、京都新聞の人と話し込んで、夜。
2008年03月02日
高城修三連歌はじめ

クレメントで始まりました、毎年恒例、高城修三の「連歌はじめ」に来ています。
JR四国の社長さんやクレメントの社長さん、元丸亀市長さん、日銀の支店長さん、民主党の国会議員さん、屋島の東照宮の総代さん、新聞社の支社長さんなど県内の重鎮な方が多く集う「連歌はじめ」は、私に取っては催事PRの市場(いちば)です。
今日は、紹興酒もそこそこに(後でしこたま飲みましたが)、インクジェットでプリントしたばかりの「農村歌舞伎」のチラシを配りまくりました。
宴もたけなわになった頃、連歌が始まりました。
発句:つり人や梅の香運ぶ瀬戸の風(共同通信社の府川浩さん)
脇:春はいずこやイージス艦(小川淳也さん)
が採用されて、三句以降へと続きます。
2008年02月20日
本日午後開催・・・
もたもたしているうちに、あした機能への仕込みを忘れてしまいまして、、
連歌講座の告知です<(_"_)>
香川県出身芥川賞作家高城修三を講師に迎えての「連歌講座」
本日午後3時より、番町の中條財団で開催です。
授業料は、3000円 ※休憩時間に三友堂のお菓子と抹茶がでます。
よかったらどうぞ! >特に、あの時の(どのときだ?)UDマンさん、となきちさん、ウサさん♪♪
講義の内容は↓の続きとなります。
http://kappadoujou.ashita-sanuki.jp/e6545.html
http://kappadoujou.ashita-sanuki.jp/e6545.html
連歌講座の告知です<(_"_)>
香川県出身芥川賞作家高城修三を講師に迎えての「連歌講座」
本日午後3時より、番町の中條財団で開催です。
授業料は、3000円 ※休憩時間に三友堂のお菓子と抹茶がでます。
よかったらどうぞ! >特に、あの時の(どのときだ?)UDマンさん、となきちさん、ウサさん♪♪
講義の内容は↓の続きとなります。
http://kappadoujou.ashita-sanuki.jp/e6545.html
http://kappadoujou.ashita-sanuki.jp/e6545.html
2008年01月15日
あしたレンガにいきませんか☆
せっかくの世界に一つの優れたお道具「あした機能」がまだ、うまく使いこなせません(><)
今回も失敗していることがわかったので、改めてご案内を。。
明日午後からお休みの人、是非ご一緒に〜〜♪♪h
http://kappadoujou.ashita-sanuki.jp/e6545.html
今回も失敗していることがわかったので、改めてご案内を。。
明日午後からお休みの人、是非ご一緒に〜〜♪♪h
http://kappadoujou.ashita-sanuki.jp/e6545.html
2008年01月12日
〜淫靡で美しい世界へのいざない〜 レンガノススメ
高城修三さぬき倶楽部
2008年新春連歌講座のご案内
さてさて、下記のとおり本年第一回めのの連歌講座をご案内いたします。
今回のお題は、「つけかた」の巻。
前句の世界をど〜〜〜〜〜〜っぷり味わって、次の句を考えるテクニックを初心者むけに教えてくださいます。
連歌の世界は、たとえば映画でいうと、高い空から町を見ていて、焦点をきゅーっと絞って「その一軒の家の物干し台でkissしている恋人達の後ろ姿にフォーカスが合う」って感じのカメラワークに似てると思います。次の瞬間は、時代は明治、思わぬ伏兵に唇を奪われて頭が真白になる女性(キャラクターはご自由に)の一人称な世界に視点が変わる、といったドキドキする展開を佳しとする世界です。
宗匠(高城修三・芥川賞作家)ご自身が、特に恋の場所で危ない展開をお好みになることがわかってきて、俄然楽しい講座になってきました。
いつもの風景が鮮やかに見えたり、なんでもなかった周辺の出来事に尽きない興味を覚えたり、アナタの世界も一段と広がることは間違いありません。
是非一度覗いてみてください!
日時・場所:2008年1月16日(水)15時〜17時 晴松亭(高松市番町、中條文化振興財団)
参 加 費:3000円(教材、抹茶、主菓子代を含む)
出欠お返事:1月14日迄に、コメントかメッセージで私マロンアルファー(世話人)までお願いします♪♪
付録:昨年12月の講座では次のような半歌仙が巻かれ、無事満尾となりましたので、昨年中途半端にご紹介し始めた興行結果を一気に貼り付けます。
()の横の漢字は、それぞれの詠み人を仮名(漢字一文字)で表しています。ご存知の方がいらっしゃるかもしれませんね!
******************
「星三つ」の巻
★表 発句 凍てついた宙(そら)に流れる星三つ (風 発句だけは、宗匠が「客」と指名した人が予め考えて読むことができる、いわば唯一の「はらみ句(予め用意した句)」が許されます。
★脇 雪かげの湯に父母と我あり (葉 凍てついた宙を見ているのは、誰なのか、どこなのか、どういうシチュエーションなのか、で空想を巡らせます。
★第三 明日のこと昔のことも夢にして (火
★四句 この世の春を謳歌する蝶 (筆
★ 五句 知らぬ顔おぼろにけむる夕の月 (火
★六句 遍路撞く鐘五剣にひびく (笛
★裏 初句 朝やけの入江のカフェで君と居る (葉 恐ろしく早起きのモーニングのあるカフェである必要がありますが。。。
★二句 産毛が光る頬に手をそえ (満 連歌では「君」とは、女が男に呼びかける言葉。ここで立場(視点)が、女から男に替わります。
★ 三句 永久(とわ)の愛誓う証しの錠をかけ (笛 この句は、この会で最も物議を醸した句です。詠み人の笛さんは、証の錠を、聖通寺山の上のチャペルの「錠の名所」のことを表したつもりだったのですが、宗匠が、、、「これは、どう考えても『貞操帯』のこととしか思えない」と主張されて、次の句は貞操帯が普及していた時代の兵士の視点に移りました。
★四句 イスタンブールの紺碧の空 (火
★五句 初めてのクルージングはエーゲ海 (筆
★六句 ぶどうの房もたわわに実り (葉
★七句 幼子が見つけて示す白い月 (朝 たわわに成っている葡萄を見ている人が、エーゲ海でクルージングをしている人から、日本の里山で子どもといる人に移ります。
★八句 うさぎの杵をみんなではやす (福
★九句 にぎやかな餅つきの音暮の街 (筆 前句(九句)がお餅をついている暮れの街=つまり冬から、十一句は「花の定座(じょうざ)」なので、春の句に一気に展開しなればなりません。そこで、
★十句 飲酒検問強化週間 (葉 ★ 取り締まりのおまわりさんなら、暮も春もお出ましになります。
★十一句 うちそろい犬も浮かれる花見酒 (輝
★挙句 春の山々鶯の声 (光 「挙句の果て」という言葉で残っている最後の句は、これから何かが始まるぞ!ではなく、これも映画の最後のようにふぅっと終わる句が秀句だそうです。
2008年新春連歌講座のご案内
さてさて、下記のとおり本年第一回めのの連歌講座をご案内いたします。
今回のお題は、「つけかた」の巻。
前句の世界をど〜〜〜〜〜〜っぷり味わって、次の句を考えるテクニックを初心者むけに教えてくださいます。
連歌の世界は、たとえば映画でいうと、高い空から町を見ていて、焦点をきゅーっと絞って「その一軒の家の物干し台でkissしている恋人達の後ろ姿にフォーカスが合う」って感じのカメラワークに似てると思います。次の瞬間は、時代は明治、思わぬ伏兵に唇を奪われて頭が真白になる女性(キャラクターはご自由に)の一人称な世界に視点が変わる、といったドキドキする展開を佳しとする世界です。
宗匠(高城修三・芥川賞作家)ご自身が、特に恋の場所で危ない展開をお好みになることがわかってきて、俄然楽しい講座になってきました。
いつもの風景が鮮やかに見えたり、なんでもなかった周辺の出来事に尽きない興味を覚えたり、アナタの世界も一段と広がることは間違いありません。
是非一度覗いてみてください!
日時・場所:2008年1月16日(水)15時〜17時 晴松亭(高松市番町、中條文化振興財団)
参 加 費:3000円(教材、抹茶、主菓子代を含む)
出欠お返事:1月14日迄に、コメントかメッセージで私マロンアルファー(世話人)までお願いします♪♪
付録:昨年12月の講座では次のような半歌仙が巻かれ、無事満尾となりましたので、昨年中途半端にご紹介し始めた興行結果を一気に貼り付けます。
()の横の漢字は、それぞれの詠み人を仮名(漢字一文字)で表しています。ご存知の方がいらっしゃるかもしれませんね!
******************
「星三つ」の巻
★表 発句 凍てついた宙(そら)に流れる星三つ (風 発句だけは、宗匠が「客」と指名した人が予め考えて読むことができる、いわば唯一の「はらみ句(予め用意した句)」が許されます。
★脇 雪かげの湯に父母と我あり (葉 凍てついた宙を見ているのは、誰なのか、どこなのか、どういうシチュエーションなのか、で空想を巡らせます。
★第三 明日のこと昔のことも夢にして (火
★四句 この世の春を謳歌する蝶 (筆
★ 五句 知らぬ顔おぼろにけむる夕の月 (火
★六句 遍路撞く鐘五剣にひびく (笛
★裏 初句 朝やけの入江のカフェで君と居る (葉 恐ろしく早起きのモーニングのあるカフェである必要がありますが。。。
★二句 産毛が光る頬に手をそえ (満 連歌では「君」とは、女が男に呼びかける言葉。ここで立場(視点)が、女から男に替わります。
★ 三句 永久(とわ)の愛誓う証しの錠をかけ (笛 この句は、この会で最も物議を醸した句です。詠み人の笛さんは、証の錠を、聖通寺山の上のチャペルの「錠の名所」のことを表したつもりだったのですが、宗匠が、、、「これは、どう考えても『貞操帯』のこととしか思えない」と主張されて、次の句は貞操帯が普及していた時代の兵士の視点に移りました。
★四句 イスタンブールの紺碧の空 (火
★五句 初めてのクルージングはエーゲ海 (筆
★六句 ぶどうの房もたわわに実り (葉
★七句 幼子が見つけて示す白い月 (朝 たわわに成っている葡萄を見ている人が、エーゲ海でクルージングをしている人から、日本の里山で子どもといる人に移ります。
★八句 うさぎの杵をみんなではやす (福
★九句 にぎやかな餅つきの音暮の街 (筆 前句(九句)がお餅をついている暮れの街=つまり冬から、十一句は「花の定座(じょうざ)」なので、春の句に一気に展開しなればなりません。そこで、
★十句 飲酒検問強化週間 (葉 ★ 取り締まりのおまわりさんなら、暮も春もお出ましになります。
★十一句 うちそろい犬も浮かれる花見酒 (輝
★挙句 春の山々鶯の声 (光 「挙句の果て」という言葉で残っている最後の句は、これから何かが始まるぞ!ではなく、これも映画の最後のようにふぅっと終わる句が秀句だそうです。
2007年12月21日
本日お昼、FM815でしゃべりまス
アンリさんの番組「レストラン、ベスパフラーゴラ」にお邪魔させていただき
クリスマスムード一色の街をみながら
連歌(何の関連があるんだ!)
について熱く語ります(。・_・。)ノ
暑苦しい語りにならなければいいが…
クリスマスムード一色の街をみながら
連歌(何の関連があるんだ!)
について熱く語ります(。・_・。)ノ
暑苦しい語りにならなければいいが…
2007年12月20日
星三つの巻、二の句
流れる星をどこから見ているか、誰がどんな状況で見ているか、自由にストーリーを作りつけます。
この句は、北国の雪のかかった岩風呂で両親と星をみているというストーリーのようです
二の句 読み人 風(仮名
雪蔭の湯に父母と我あり
この句は、北国の雪のかかった岩風呂で両親と星をみているというストーリーのようです
二の句 読み人 風(仮名
雪蔭の湯に父母と我あり
2007年12月20日
「星三つ」の巻発句
昨日の連歌会は、高城修三宗匠のもと、三時間半を費やして、めでたく半歌仙(18句)を満尾(挙句まで作り完成すること)することができました。
まずは、発句からご紹介しますね
読み人 波(仮名)
発句
凍てついた宙に流れる星三つ
次は、二の句を紹介しますが、ご興味のある人はご自分ならどんな句をつけるか考えてみてくださいね(。・_・。)ノ
二の句のおもなルールは
発句と同じ季語を使うことと、77で纏めること。です。
まずは、発句からご紹介しますね
読み人 波(仮名)
発句
凍てついた宙に流れる星三つ
次は、二の句を紹介しますが、ご興味のある人はご自分ならどんな句をつけるか考えてみてくださいね(。・_・。)ノ
二の句のおもなルールは
発句と同じ季語を使うことと、77で纏めること。です。
2007年12月19日
変な人の巣窟
 今日は番町で連歌会のち雉鍋宴会中
今日は番町で連歌会のち雉鍋宴会中もともと変わった人の巣窟でしたが今日は、さらに変わった人が初参加したので、ざっとプロフィールを紹介しますね!。
年齢不詳
いい香りがする
山高帽をずっと被っていて
話の始めには必ず指を鳴らし
ビアーはまだある?と聞く
高松高校山岳部出身
大好きなんですけど、こんな人(・∀・)
2007年12月17日
レンガノススメ
みなさんはレンガと聞くと何を想像されますか?
赤いあれですかね
今日は煉瓦ではなくて,もうひとつのレンガ,「連歌」のことをご紹介します。
連歌とは,その名のとおり,歌を連ねる遊びです。
575 の次は 77
また 575 と,誰かが詠んだ歌を違う人が,その句を受けて,しかもイメージを転じて,句を作っていくゲームです。
3人~20人くらいの人が集まって,これをやります。
この中には,通常「宗匠」と言われる,句の採否を決める人
「客」と言われる 発句(一番初めに詠む句)を詠む人
がいます。
連歌にはいつくかのルールがあります。
例えば
1.18句(半歌仙)では1回,36句(歌仙)では2回,それぞれ2~5句を続けて,「恋」の句を読まなければならない。
2.月の定座が何句目かにありますが,そこでは月について詠まなければならない。
3.最後から二番目は「花の定座」ですが,ここでは「桜」を「花」という言葉に置き換えて読まなければならない。
このほか,
二句前のイメージを繰り返してはならない(観音開きを嫌う)
同じ人が二句続けて投句してはならない(漁り禁止)
などのルールもあります。
連歌って,ルールがあって難しそう!!!と思われましたか? しかし,それは違います!!
たとえば,アナタ♪ 今の心境を575で詠んで見てください といわれたら,ちょっと戸惑いませんか(戸惑わない?失礼しました!!)
たとえば,575で,クリスマスというキーワードを入れて,最後は体言止め(名詞でとめる)で,作ってみてください。
といわれたら,どうでしょう。。。 かえってこっちの方が作りやすいと思いませんか?(あ,思わない,失礼しました!)
連歌の起こりは万葉集に遡ります。最も盛り上がったのは江戸時代。700年もの間上は天井人から町人まで,日本人に愛されてきた連歌は,「みんなでつくる共同の芸術」です。
日本の芸術の多くには実は,一人で最初から最後まで作るのではなくて,この部分はきみ,この部分は私,この部分はあの人,と役割分担して素晴らしいものを生み出すという特徴があります。茶道などはこの典型だと思います。
しかし,現在では,国語の教科書で連歌は教えてくれません。日本史に一部出てくる程度です。
これは,明治以降のヨーロッパから入ってきた考え(一人で最初から最後までやるのが芸術,著作権が発生する)の影響だそうで,正岡子規は「連歌は文学にあらず」と一時激しい排斥をしたそうです。
よく知られている松尾芭蕉は,俳句の人として教えられますが,彼は実は連歌師でした。
発句を詠む「客」として,諸国の連歌会(頻繁にあった)を廻り,お礼やお食事と宿を提供されていたそうです。
有名な句
五月雨を集めて速し最上川
も実は連歌の発句であり,この後二句目から延々と35句が続いているのです。
しかし,どういうわけか,この事実には言及されず,山頭火が行脚して一句ずつ作っていった紀行文のように扱われているのです。
「連歌にはルールがあるけれど,それは魅力的な考えを次から次へと生み出す知的な装置である。」
ということに気付いて以来,下手でなかなか宗匠に句を採用されないながらも,連歌に夢中なのです。
これまでは京都で開催されることが多かった連歌の会を,高松で持つ事になりましたので,下記にてご案内します。
ご興味のある方は,最初は同席されているだけで大丈夫ですので,一度みにいらっしゃいませんか?
記
名称:高城修三の連歌会@晴松亭
場所:中條文化振興財団(高松市番町)
日時:2007年12月19日(水) 午後3時~
宗匠:高城修三先生
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%9F%8E%E4%BF%AE%E4%B8%89
参加費:3000円(お菓子と抹茶付)
世話人:マロン
コメントかメッセージでどうぞ
※午後6時からきじ鍋忘年会(会費5,000円)もあります。こちらにもご興味がある方はお問い合わせ下さい♪
※1月~3月は,毎月第三水曜日の午後3時~午後5時に,連歌講座が開催されます。併せてご案内申し上げます。
付録
この夏に,ある素敵な経営者とデザイナーと3人でフィリピンカフェで連歌で盛り上がったときに,できた連歌(途中)です。
発句: 常夏の異国のカフェでワイン開け
流れる歌はバラードばかり
新品のウェッジソール履きなれて
老舗の女将月曜day off
逢うときは巻上げた髪おろします
昔の情念燃え上がるかな。。。
って,いきなり,天城越えの世界に突入してしまって,収集つかない~~~
赤いあれですかね

今日は煉瓦ではなくて,もうひとつのレンガ,「連歌」のことをご紹介します。
連歌とは,その名のとおり,歌を連ねる遊びです。
575 の次は 77
また 575 と,誰かが詠んだ歌を違う人が,その句を受けて,しかもイメージを転じて,句を作っていくゲームです。
3人~20人くらいの人が集まって,これをやります。
この中には,通常「宗匠」と言われる,句の採否を決める人
「客」と言われる 発句(一番初めに詠む句)を詠む人
がいます。
連歌にはいつくかのルールがあります。
例えば
1.18句(半歌仙)では1回,36句(歌仙)では2回,それぞれ2~5句を続けて,「恋」の句を読まなければならない。
2.月の定座が何句目かにありますが,そこでは月について詠まなければならない。
3.最後から二番目は「花の定座」ですが,ここでは「桜」を「花」という言葉に置き換えて読まなければならない。
このほか,
二句前のイメージを繰り返してはならない(観音開きを嫌う)
同じ人が二句続けて投句してはならない(漁り禁止)
などのルールもあります。
連歌って,ルールがあって難しそう!!!と思われましたか? しかし,それは違います!!
たとえば,アナタ♪ 今の心境を575で詠んで見てください といわれたら,ちょっと戸惑いませんか(戸惑わない?失礼しました!!)
たとえば,575で,クリスマスというキーワードを入れて,最後は体言止め(名詞でとめる)で,作ってみてください。
といわれたら,どうでしょう。。。 かえってこっちの方が作りやすいと思いませんか?(あ,思わない,失礼しました!)
連歌の起こりは万葉集に遡ります。最も盛り上がったのは江戸時代。700年もの間上は天井人から町人まで,日本人に愛されてきた連歌は,「みんなでつくる共同の芸術」です。
日本の芸術の多くには実は,一人で最初から最後まで作るのではなくて,この部分はきみ,この部分は私,この部分はあの人,と役割分担して素晴らしいものを生み出すという特徴があります。茶道などはこの典型だと思います。
しかし,現在では,国語の教科書で連歌は教えてくれません。日本史に一部出てくる程度です。
これは,明治以降のヨーロッパから入ってきた考え(一人で最初から最後までやるのが芸術,著作権が発生する)の影響だそうで,正岡子規は「連歌は文学にあらず」と一時激しい排斥をしたそうです。
よく知られている松尾芭蕉は,俳句の人として教えられますが,彼は実は連歌師でした。
発句を詠む「客」として,諸国の連歌会(頻繁にあった)を廻り,お礼やお食事と宿を提供されていたそうです。
有名な句
五月雨を集めて速し最上川
も実は連歌の発句であり,この後二句目から延々と35句が続いているのです。
しかし,どういうわけか,この事実には言及されず,山頭火が行脚して一句ずつ作っていった紀行文のように扱われているのです。
「連歌にはルールがあるけれど,それは魅力的な考えを次から次へと生み出す知的な装置である。」
ということに気付いて以来,下手でなかなか宗匠に句を採用されないながらも,連歌に夢中なのです。
これまでは京都で開催されることが多かった連歌の会を,高松で持つ事になりましたので,下記にてご案内します。
ご興味のある方は,最初は同席されているだけで大丈夫ですので,一度みにいらっしゃいませんか?
記
名称:高城修三の連歌会@晴松亭
場所:中條文化振興財団(高松市番町)
日時:2007年12月19日(水) 午後3時~
宗匠:高城修三先生
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%9F%8E%E4%BF%AE%E4%B8%89
参加費:3000円(お菓子と抹茶付)
世話人:マロン
コメントかメッセージでどうぞ

※午後6時からきじ鍋忘年会(会費5,000円)もあります。こちらにもご興味がある方はお問い合わせ下さい♪
※1月~3月は,毎月第三水曜日の午後3時~午後5時に,連歌講座が開催されます。併せてご案内申し上げます。
付録
この夏に,ある素敵な経営者とデザイナーと3人でフィリピンカフェで連歌で盛り上がったときに,できた連歌(途中)です。
発句: 常夏の異国のカフェでワイン開け
流れる歌はバラードばかり
新品のウェッジソール履きなれて
老舗の女将月曜day off
逢うときは巻上げた髪おろします
昔の情念燃え上がるかな。。。
って,いきなり,天城越えの世界に突入してしまって,収集つかない~~~