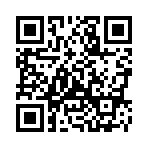› マロンの冒険 › D-net
› マロンの冒険 › D-net2010年02月15日
森林療法講座・受講メモ

昨日はドングリランドで開催の「森林療法」の講義と体験(東京農業大学 上原巌先生)に午前中だけ参加させてもらいました。
以下はレクチャーメモ★
日本は自殺が多い国(50歳以上の高齢者が多い)敬老の日に好んで自殺する
森林療法の効能
成人病に効く
交通事故後遺症にいい結果
カウンセリングを森で聞くことで、屋内では聞き出せないことが出てくる
地域山林の回復は同時に作業する人の人間性の回復
現在の日本における森林セラピーはガイド中心
ヨーロッパでは保養地認定は10年かかる
北海道中頓別町 高齢化率高い・病院は1軒・高血圧多い・森林療法を実施した結果平常時血圧下がり、1年間10500円(町民ひとりあたりの医療費)医療費が減った
福島県只見町(自殺率が高い) →自殺予防の森林療法を実施中
香川県での実施のすすめ
これまでの事例を参考にすると
運動・健康増進
余暇
寝たきり・引きこもり予防
骨粗しょう症の予防
肥満予防
気分転換
認知症の予防
脳を活性化する
ために、森林療法を活用してはいかが
具体的には
定期的に森林散策を継続する
健康状態、生活習慣の変化、通院
高齢者施設(社会福祉施設)との連携
香川の医療費削減を目指す
★森の幼稚園
1960年デンマークで発足
園舎・園庭を持たない
フレーベル(森林技術者)が提唱
2007年 400箇所@ドイツ
特長
身近な森林環境を利用
言葉の発達が通常の幼稚園より早い
長期欠席がすくない
感情が安定する
五感の発達
友達づくりが上手になる
一人遊びもできる
学習面も良好である
企業における森林療法
転地効果
有給休暇を使って社員に機会を提供する経営者あり
企業におけるメンタルヘルスの効果
自分の木をみつけて自分の木とすること
グループで癒しの場所を見つける
自己肯定感が高まる
森林療法の効用をまとめると
高血圧の改善
高コレステロール血症と糖尿病の予防に効果的
体重の減少
呼吸器循環器機能の向上
動脈硬化や狭心症の予防
γ-GTPの減少
Nk細胞(免疫機能)の活性化
ストレスの改善
気分の改善
認知症のコミュニケーション活性化
自己肯定感の向上
★森林療法体験を通して
2月だというのに、枯葉に寝転がるのがそんなに寒くなかった。
その場では眠くならなかったが、帰宅後眠くなった。
青木という木の葉っぱは火傷に効く。そのまま貼り付けるべし
ねずみさしという木の枝は精油成分が入浴剤になる
ヒノキを細かく刻んで袋にいれても入浴剤になる
枝の葉が枯れても落ちない木は、「次の新芽を守るDNA」
※写真は、上原先生が肌身離さずつれて歩いておられる「ニングル」
アイヌの森の妖精で、エンジュの木で出来ている
アイヌでは、赤ちゃんのおしゃぶりも木で作られるが、それを削るのは彫刻が巧い人ではなく、村で一番「心の綺麗な人」。いじわるな人が彫ると、おしゃぶりが苦くなるからだそうだ。
http://ameblo.jp/aratakyo/entry-10458517313.html
2009年05月30日
「夏の森のチャリティトーク&コンサート」 活動記録を遡る

実は今月から2年間、長らく幽霊会員をしていたある団体の理事に就任することになりました。
3月に電話がかかってきて、「変えたいんだ」というその人の思いを聞いて共感したものの、「会員ですら幽霊の自分は無理なような。。」と、腰が引けた状態のまま、返事を延ばし延ばしにしているうちに後に引けなくなったといったのが正味な顛末です。
先日、案内された理事会に陪席(まだ前年度の会だったので)したものの、そこで繰り広げられる議論の真面目さ、切実さ、厳しさに圧倒されて一言も発言できず、その後は、しばらくはなすすべもなく、ただ理事内の活発な発言が繰り広げられるMLを眺め続けていました。
「すっごく正論なんだけど、そそられないんだよなあ」
って感じることって、結構ありますよね。
正しい有意義な活動をしていても、現実的に母集団を増やしたいと思ったら、選挙でいうところの浮動票保持者みたいな人たちに「お?」と思わせる仕掛けが必要で、その仕掛けは最初はかなりミーハーなものや本能のどこかに直結できるものだったりすること、その団体の目的とは関係ないけれどその人の目的や必要がそこにある、、なんてこともポイントだったりします。
そんなきっかけで深く考えずに足を入れたところ、足を踏み入れた場所の本来の魅力に後で気がつく、、という流れ。
本来の意義がわかっていてそこで活動している人を大切にすることとや、しくみを見直して整備することや、誰かが無理をしているのをちゃんと見るってこととと同時に、一方で、こんな角度からの目線も必要なのかなと他のことを観ていても感じていました。
浮動票保持者の代表みたいな私に声がかかった理由は、浮動票保持者が、そこに足を向けたくなるような「そそらられる」仕掛けを一緒に作ってね。。ということだったのかな。。
と今朝ようやく腑に落ちたような気がします。(間違ってるかもしれないけどね)
てことで、準備その1
あまずは5年前の活動をレポートして、ここに格納します。以後レポートが続くかもしれません。
よろしければ、回想におつきあいください。
***********************
私は2003年の終わりにももどんさん(白井女史)に教えてもらってドングリランドを初めて知りました。
その頃は、知的ハンディを持つお子のママを応援している人の、香川県での2回目の講演会の場所探しをしているところだったので、同時開催のピアノコンサートも含めて、ここが会場なら素敵だなあと、例によって妄想が始まりました。そして
「ビジターセンターにグランドピアノを持ち込んで、講演会と梅田玲奈のミニコンサートをやりたいね」
とももどんさんに口にしてしまったところ、その頃の理事会のみなさんのご理解、ちくわ(竹環)の会の甚大なるご協力、そしてなによりももどんの孤軍奮闘ともいえる活躍で、妄想が現実になりました。
ドングリランドでのコンサート開催に際しては、2つ、クリアしないといけないことがありました。
一つは、センターの床に重さ300キロのグランドピアノを置いても強度は大丈夫かということ。
もう一つは、車椅子を必要とする人がお手洗いに行ったり、会場内を移動できる構造になっているか、また、なっていない個所はどのようにフォローするか
ということでした。
一つめは、県の担当者の方にも問い合わせてもらって「問題ない」ということになりクリア。
二つめは、ちくわの会の人たちがが車椅子を運んだり、子どもを抱っこして階段の上り下りをしてくれることになりました。
また、山の自然の音はそもそも素敵なので、ピアノが参加するとどんな感じになるのかな、と少し心配してましたが、フタをあけてみればっランドの空気とスタンウェイのピアノの音がすごく調和して、本当に素敵な空間を作ることができました。
この時の聴衆の大半は、知的ハンディを持つお子さんを育てるママ達だったのですが、その中には、ピアノの音色を聞いて、泣いてる人もいました。
連れて来てもらった子どもたちは、センター横を少し降りた場所で、竹の水鉄砲を作ったり、竹水ようかんを作ったりして、ちくわの会の頼もしい人たちが思いっきり遊ばせてくれました。
「子どもを外で元気に遊ばせてもらいながら、素敵なピアノの音を、ひとりでゆっくりと聞いたことはなかった」という言葉をもらったことは、「そういうイベントができて良かった」という感慨と同時に、「こんなことがなければ気持ちが休まる時間がほとんどないということなんだ」という感想に繋がり、いろいろな意味で、考えさせてもらうきっかけになりました。
この時の参加者のほとんどは、ドングリランドの場所も存在も知りませんでした。「子連れで行けて、梅田玲奈のピアノを聴くことができる」という目的がなければ、その後ももしかしたら足を運ぶことはなかった場所だったかもしれません。でも妄想が現実になった結果、ママ達がドングリランドの魅力を知り、以後、「ドングリランド」は彼女達が何かを催す会場候補の一つに加わりました。
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Sumire/4346/