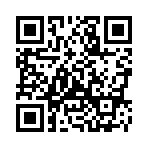› マロンの冒険 › 茶の湯
› マロンの冒険 › 茶の湯2011年03月21日
血屋敷井戸義捐金茶会ご報告(内容更新3月22日午後)
このブログで告知いたしました、20日開催の、血屋敷井戸義捐金茶会について、お約束により、これよりご報告申し上げます。
まずは義捐金と寄付してくださった人の情報から。
★義捐茶(抹茶、コーヒー、ハーブティ) 売り上げ金 49,500円が集まりました。
★義捐金は、以下の方々のご芳志により 124,730円が集まりました。
小川将信さま 10口
石川由美さま 1口
蓮井愛渚さま
蓮井里渚さま
木村美香さま
武井伊織さま
前田 侑さま 2口
赤松未枝子さま 2口
橋本卓也 1口
岸 達也さま 3口
牟礼し(糸糸)津子さま
高橋司枝さま
御城俊宏さま 10口
小川 凛さま
野崎千恵さま 5口
別所治親さま
別所千尋さま
蓮井隼介さま
新和開発さま 10口
香川がん患者おしゃべり会さま 5口
ノイリー・プラットさま 1口
高地正人さま 1口
池田靖夫さま 1口
増田裕司さま 3口
多田裕彦さま 5口
たみ家さま 1口
金澤賢治さま 5口
ペンペンさま 3口(追加義捐金)
受付順、56名(匿名希望の方を含む)
★ご協力いただいた方々
宗家くつわ堂さま(瓦せんべい)
原ヲビヤ園さま(茶碗、水屋道具一式貸与、義捐金)
三友堂さま(机貸し出し、お菓子割引)
フェアトレードコーヒーhalqaさま(コーヒー豆1キロ)
中條文化振興財団さま(銘銘盆貸与)
セカンドステージ薮内さま(差し入れシフォンケーキ)
NHK高松放送局さま(事前告知・取材・ニュース)
杉ノ内由紀さま(取材・事前告知・四国4局ネットラジオ番組での紹介)
★★義捐茶売り上げ+義捐金=174,230円
★★★
当日サポートしてくれた人たち
@るいまま組
るいまま(準備・会場設営・種々声かけ)
るみるみ(会場設営・コーヒーミルレスキュー)
みっけ(義援金受付・街頭よびかけ)
ぴよ旦那(カフェ道具提供・コーヒーブース担当・シフォンケーキ提供)
ぽんた(会場設営・義援金受付)
GONBE(お抹茶ブース支援)
さっち(会場設営・街頭よびかけ・報道支援)
ぴよ(会場片付け・告知支援)
かいと(会場設営・接待)
みっち(水支援)
姫(水支援)
@オリーブガイナーズ
じゅんじゅん(カフェブース支援・接待)
@エールみらい
てるちゃん(オリーブの木提供、看板用コンパネ調達、ハーブティ寄付、お菓子寄付誘致、水支援)
てるちゃん相方(同上)
@あしたさぬき
となきち(街頭での呼びかけ・水支援)
くりす(水支援)
UDマン(エール)
@デューク更家公認ウォーキングスタイリスト
ほのきち(街頭での呼びかけ・井戸ガイド補助・水支援)
@高畠守徹武者小路千家社中
川西洋子(井戸ガイド補助)
原ヲビヤ園(準備)
@せとちとせとら
せとちとせ(凱旋ライブ)
関わってくれたみなさんの思いがいっぱいつまった、174,230円を持って、明日(本日)四国新聞(日本赤十字社)に行って寄付手続きをしてまいります。
なお、
血屋敷井戸の詳細については、この井戸の復元に情熱を注ぎ続けらている築港万次郎さんのこちらのHPをご参照ください。
また、小説源内コードには、この血屋敷井戸にまつわるエピソードが鏤められています。是非ご一読を!
生駒家の家紋と築城の天才といわれた黒田如水の家紋の刻まれた石が組み込まれた「血屋敷井戸」。
この井戸の命名の理由や、井戸の存在理由等には、諸説あると思います。
このHPで紹介されている築港万さんの説には、「ええっ?」と驚くようなことや、「飛躍しすぎでは?」と感じる部分がいくつかあります。
が、私は、一度壊されてバラバラの石になっていた血屋敷井戸の復元が高松のまちを幸せにすると信じて、壊された井戸の復元への説得作業に人生の多くの時間を捧げている築港万さんの説を尊重し、讃岐のまちと民を災いから守るためにこの井戸を作った生駒親正候の、この大切な遺跡の御霊が喜ぶことに、これからも井戸を活用していきたいと思っています。
今回、告知から始まって、準備、当日不足品調達、受付、お茶点て、茶碗洗い、コーヒー、ハーブティ、お菓子調達、お茶調達などを支えてくださった皆さんのこと、また、本日の様子については、るいままとしての365日に詳しく紹介していただいていますので、ご参照ください。
実は、この井戸の復元が完了した3月13日(日)に、築港万さんの依頼で、中條財団のゴッドマザーと、武者小路千家のお茶の普及に尽力されている三友堂社長の大内さんのご協力を得て、井戸の復元を記念した供茶および記念茶会を実施しました。
供茶が無事終わった後、地震の報道で、テレビで町の半分の人たちが津波でいなくなってしまったところの町長さんが、被災時の様子を生々しく話された後、「何か全国のみなさんにおっしゃりたいことは?」と聞かれ、「とにかく、水と食料を・・・」と言いかけて、それまでは気丈にお話していたのに、言葉が詰まって後が続かなくなってしまった映像を見て涙が込み上げました。そして、自分にいったいなにができるんだろうと、考え始めました。
復元記念供茶でいただいた水屋見舞の15000円を義捐金に寄付しようかと考えたけれど、もうちょっと考えて、せっかくなら、東北の人たちを助けたいと思っている高松市民はほかにもいるんじゃないか、そんな人たちと、応援したい気持ちをわかちあえる方法があるんじゃないかと思い、ここまで考えたときにに、「義捐金茶会」を思いつきました。
いただいた15000円を原資にして、お茶とお菓子を買って、あの井戸でお茶を点て、お客さまからは500円をいただいて、その売上金を寄付しようと。15000円から少しでも増えてたらいいなと。
お茶というのは、不思議な役割があって、人を「あ、お茶飲みに行こう」と動かす原動力にもなるし、人と人をつなげる触媒にもなる、疲れた人を慰める一塊の暖にもなります。どうか、「お茶」が、被災した人が、明日からちょっとでも笑っていられる、日本中のみんなが応援していることを知って勇気を持ってもらえる媒体になりますように、と願って、20日の井戸の使用許可をもらって、水曜日に実施を決めました。
思いついたときには、誰にも手伝いを頼んでいなかったので、私がお茶を点てて、築港万さんにお茶碗洗いを手伝ってもらって、井戸の説明をしたり、、お菓子とのセットはセルフで、、なんてこじんまりした「茶会」を想定していました。
そして、自分の周りの人に少しずつメールをしました。
ところが、これをキャッチしたるいままがすかさず反応してくれて、まず「いくよ」「手伝いはおるん?」「ストーブはあるん?」というメールから始まって、あっという間にあのギガ拡散装置で紹介してくれました。メールで少しずつ案内を送った翌日にはすでにNHKさんやFMの取材があり、言い出した私があたふたと取り残され感を感じるほと、それは、精力的なものでした。
貴重な日曜日を茶会に使ってくださった善意の人100人と、義捐金や義捐品をくださった56人(武者小路千家高畠先生社中の方を多く含む)と、長時間立ちっぱなしで茶会を手伝ってくれた10人以上の人、そして、せとちとせさんの魂の歌のお陰で、この、あえておどろおどろしい名前がつけられた血屋敷井戸跡が、とても暖かな、光が溢れるような、ずっと座っていたい、気持ちのいい気がぐんぐん回っているような場所に戻ったと感じました。
ここに、今回茶会に関わってくれた、すべての方に、心から、感謝します。
ありがとうございました。
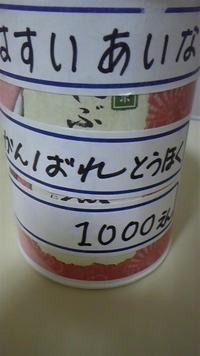

まずは義捐金と寄付してくださった人の情報から。
★義捐茶(抹茶、コーヒー、ハーブティ) 売り上げ金 49,500円が集まりました。
★義捐金は、以下の方々のご芳志により 124,730円が集まりました。
小川将信さま 10口
石川由美さま 1口
蓮井愛渚さま
蓮井里渚さま
木村美香さま
武井伊織さま
前田 侑さま 2口
赤松未枝子さま 2口
橋本卓也 1口
岸 達也さま 3口
牟礼し(糸糸)津子さま
高橋司枝さま
御城俊宏さま 10口
小川 凛さま
野崎千恵さま 5口
別所治親さま
別所千尋さま
蓮井隼介さま
新和開発さま 10口
香川がん患者おしゃべり会さま 5口
ノイリー・プラットさま 1口
高地正人さま 1口
池田靖夫さま 1口
増田裕司さま 3口
多田裕彦さま 5口
たみ家さま 1口
金澤賢治さま 5口
ペンペンさま 3口(追加義捐金)
受付順、56名(匿名希望の方を含む)
★ご協力いただいた方々
宗家くつわ堂さま(瓦せんべい)
原ヲビヤ園さま(茶碗、水屋道具一式貸与、義捐金)
三友堂さま(机貸し出し、お菓子割引)
フェアトレードコーヒーhalqaさま(コーヒー豆1キロ)
中條文化振興財団さま(銘銘盆貸与)
セカンドステージ薮内さま(差し入れシフォンケーキ)
NHK高松放送局さま(事前告知・取材・ニュース)
杉ノ内由紀さま(取材・事前告知・四国4局ネットラジオ番組での紹介)
★★義捐茶売り上げ+義捐金=174,230円
★★★
当日サポートしてくれた人たち
@るいまま組
るいまま(準備・会場設営・種々声かけ)
るみるみ(会場設営・コーヒーミルレスキュー)
みっけ(義援金受付・街頭よびかけ)
ぴよ旦那(カフェ道具提供・コーヒーブース担当・シフォンケーキ提供)
ぽんた(会場設営・義援金受付)
GONBE(お抹茶ブース支援)
さっち(会場設営・街頭よびかけ・報道支援)
ぴよ(会場片付け・告知支援)
かいと(会場設営・接待)
みっち(水支援)
姫(水支援)
@オリーブガイナーズ
じゅんじゅん(カフェブース支援・接待)
@エールみらい
てるちゃん(オリーブの木提供、看板用コンパネ調達、ハーブティ寄付、お菓子寄付誘致、水支援)
てるちゃん相方(同上)
@あしたさぬき
となきち(街頭での呼びかけ・水支援)
くりす(水支援)
UDマン(エール)
@デューク更家公認ウォーキングスタイリスト
ほのきち(街頭での呼びかけ・井戸ガイド補助・水支援)
@高畠守徹武者小路千家社中
川西洋子(井戸ガイド補助)
原ヲビヤ園(準備)
@せとちとせとら
せとちとせ(凱旋ライブ)
関わってくれたみなさんの思いがいっぱいつまった、174,230円を持って、明日(本日)四国新聞(日本赤十字社)に行って寄付手続きをしてまいります。
なお、
血屋敷井戸の詳細については、この井戸の復元に情熱を注ぎ続けらている築港万次郎さんのこちらのHPをご参照ください。
また、小説源内コードには、この血屋敷井戸にまつわるエピソードが鏤められています。是非ご一読を!
生駒家の家紋と築城の天才といわれた黒田如水の家紋の刻まれた石が組み込まれた「血屋敷井戸」。
この井戸の命名の理由や、井戸の存在理由等には、諸説あると思います。
このHPで紹介されている築港万さんの説には、「ええっ?」と驚くようなことや、「飛躍しすぎでは?」と感じる部分がいくつかあります。
が、私は、一度壊されてバラバラの石になっていた血屋敷井戸の復元が高松のまちを幸せにすると信じて、壊された井戸の復元への説得作業に人生の多くの時間を捧げている築港万さんの説を尊重し、讃岐のまちと民を災いから守るためにこの井戸を作った生駒親正候の、この大切な遺跡の御霊が喜ぶことに、これからも井戸を活用していきたいと思っています。
今回、告知から始まって、準備、当日不足品調達、受付、お茶点て、茶碗洗い、コーヒー、ハーブティ、お菓子調達、お茶調達などを支えてくださった皆さんのこと、また、本日の様子については、るいままとしての365日に詳しく紹介していただいていますので、ご参照ください。
実は、この井戸の復元が完了した3月13日(日)に、築港万さんの依頼で、中條財団のゴッドマザーと、武者小路千家のお茶の普及に尽力されている三友堂社長の大内さんのご協力を得て、井戸の復元を記念した供茶および記念茶会を実施しました。
供茶が無事終わった後、地震の報道で、テレビで町の半分の人たちが津波でいなくなってしまったところの町長さんが、被災時の様子を生々しく話された後、「何か全国のみなさんにおっしゃりたいことは?」と聞かれ、「とにかく、水と食料を・・・」と言いかけて、それまでは気丈にお話していたのに、言葉が詰まって後が続かなくなってしまった映像を見て涙が込み上げました。そして、自分にいったいなにができるんだろうと、考え始めました。
復元記念供茶でいただいた水屋見舞の15000円を義捐金に寄付しようかと考えたけれど、もうちょっと考えて、せっかくなら、東北の人たちを助けたいと思っている高松市民はほかにもいるんじゃないか、そんな人たちと、応援したい気持ちをわかちあえる方法があるんじゃないかと思い、ここまで考えたときにに、「義捐金茶会」を思いつきました。
いただいた15000円を原資にして、お茶とお菓子を買って、あの井戸でお茶を点て、お客さまからは500円をいただいて、その売上金を寄付しようと。15000円から少しでも増えてたらいいなと。
お茶というのは、不思議な役割があって、人を「あ、お茶飲みに行こう」と動かす原動力にもなるし、人と人をつなげる触媒にもなる、疲れた人を慰める一塊の暖にもなります。どうか、「お茶」が、被災した人が、明日からちょっとでも笑っていられる、日本中のみんなが応援していることを知って勇気を持ってもらえる媒体になりますように、と願って、20日の井戸の使用許可をもらって、水曜日に実施を決めました。
思いついたときには、誰にも手伝いを頼んでいなかったので、私がお茶を点てて、築港万さんにお茶碗洗いを手伝ってもらって、井戸の説明をしたり、、お菓子とのセットはセルフで、、なんてこじんまりした「茶会」を想定していました。
そして、自分の周りの人に少しずつメールをしました。
ところが、これをキャッチしたるいままがすかさず反応してくれて、まず「いくよ」「手伝いはおるん?」「ストーブはあるん?」というメールから始まって、あっという間にあのギガ拡散装置で紹介してくれました。メールで少しずつ案内を送った翌日にはすでにNHKさんやFMの取材があり、言い出した私があたふたと取り残され感を感じるほと、それは、精力的なものでした。
貴重な日曜日を茶会に使ってくださった善意の人100人と、義捐金や義捐品をくださった56人(武者小路千家高畠先生社中の方を多く含む)と、長時間立ちっぱなしで茶会を手伝ってくれた10人以上の人、そして、せとちとせさんの魂の歌のお陰で、この、あえておどろおどろしい名前がつけられた血屋敷井戸跡が、とても暖かな、光が溢れるような、ずっと座っていたい、気持ちのいい気がぐんぐん回っているような場所に戻ったと感じました。
ここに、今回茶会に関わってくれた、すべての方に、心から、感謝します。
ありがとうございました。
2010年01月11日
2009年12月31日
遊にあらず芸にあらず

ついに2009年最後の日でございます。
年賀状を書いたら年越しそばをさくっと作って、年明け準備して、後は6日と11日お当番の茶会のストーリー詰めます〜〜
テーマは6日は「おもかげ」=親しく大切な人にまつわるものを絡めて、13席のところどころにはチェアマンをお招きし、その方の「大切な思い」を宝物と一緒に愛でていただく予定です。マロン的には今回の『大切な人」とは自分をもっとも愛してくれた人である父を彷彿とさせる仕立てにしたいと思っています。お正月明けなのであまり重くならないように気をつけてねと自分に言い聞かせつつ。。
そして11日(点心)では、「マザーポート(母港)」というテーマで通してみたいとおもっています。といっても点心のお料理はテーマごと「鬼才」野原氏@永楽亭に丸投げしているので、自分は、テーマにあった「あるもの」を1点だけ飾り、お料理を差し上げながら、多くの島のマザーポートである高松の近未来に思いをはせるお話をしたいと思っています。
どうなるかは、ふたを開けてみないと自分でもわからない(毎度のこと)ですが、楽しんで堪能しながら作りこみたいと思っていますので、ご興味ある方は是非ご参加くださいませ!
内田繁茶の湯展「遊にあらず芸にあらず」at SOUVENIR
Switch入るのが遅いことは今に始まったわけではないけれど、時々自分と付き合いきれない、ほとほと愛想が尽きそうになることがございます
来年はもう少し折り合いつけられるとよろしなと。
もしかしたら次の投稿は来年かも知れませんのでとりあえずご挨拶をいたします。
みなさまどうぞ良いお年をお迎えください
(。・_・。)ノ
2009年07月05日
天の川デート考
今日はジョージナカシマ記念館茶会の0番茶席のチケットが幸運にも手に入ったので、敬愛するMii師匠とともに朝から桜製作所にお邪魔していました。
一席めは、武者小路千家家元内弟子の高畠先生が席主を務める天遊卓の立礼席。
本席の軸は俵屋宗達の筆の入った画讃で、彦星が織姫に会うために川を渡るのに、とても急いでいるため、着物の裾を膝まで上げて水に入っているよ。。という意味の歌が書かれているロマンチックなものでした。
マロンがお茶を戴いた3碗めは、昔の女性がお歯黒に使っていた器を茶碗に見立てた金魚柄の染付の平茶碗。
茶入れは、蓋で隠れる部分にまで蒔絵の入った中継で、江戸期中期のもの。
主菓子は三友堂の渾身の創作菓子で、コシ餡に黒砂糖の香り豊かなゼリーが巻き付いて金星が鏤められている「星の雫」。
ヘタしたら、美術館に所蔵されてしまって、触ることもままならないような貴重なお道具が惜しげもなく披露された贅沢な贅沢な御席でした。
二席めは、記念館館長の永見会長が席主を務める桜製作所製の立礼机を用いた薄茶席(裏千家流)です。

本席の床には、「木の聲を聴け」と、ジョージナカシマ先生が常におっしゃっていた言葉を永見会長がそのまま心を込めて筆で書かれたという、味のある御軸がかかっていました。

水指、茶入(ウォールナット)、蓋置、茶杓(オリーブの木)、建水、菓子器がすべて桜製作所製の木製。

木の素敵さをこれでもかこれでもかと感じさせてくれるような、文字通り「木の聲が聴こえる」お茶席でした。

そして、お茶会終了後は、久しぶりの伏見塾に参加し、相変わらずの微に入り細に入りの面白い講義内容を久しぶりに堪能しました。
今日の講義は、待ち合いについて。各流派の踏み石の置き方や石の質、数、大小、にじり口からの距離、腰かけのこと、塵穴のことなどを詳しく教えて戴けました。
伏見先生の講義を生で聴けることは香川県で住んでいる人の特権ともいえるんだということが、昨日の二蝶での先生の米寿のお誕生会で改めて実感いたしまして、「また、万障繰り合わせて来なくちゃ」と再認識した次第です。次の講義は11日午前10時から。ご興味のある方は、ご一報ください。
そして、先生のご用意くださったお菓子も七夕に因んだ「天の川」でした。

好きな人と一年に一度しか逢えないなんて気の毒、、なんて言われることの多い彦星と織姫ですが、
たとえ一年に一度でも、大好きな人と丸一日、確実にデートできるなら、それはそれで羨ましい話。
やっとのことで約束に漕ぎ着けたとしても、その日確実に大好きな人に逢えるかどうかなんて、本当はわからないから。。
夏の始まりらしい一日が終わり、雨の香りがしてきました。
一席めは、武者小路千家家元内弟子の高畠先生が席主を務める天遊卓の立礼席。
本席の軸は俵屋宗達の筆の入った画讃で、彦星が織姫に会うために川を渡るのに、とても急いでいるため、着物の裾を膝まで上げて水に入っているよ。。という意味の歌が書かれているロマンチックなものでした。
マロンがお茶を戴いた3碗めは、昔の女性がお歯黒に使っていた器を茶碗に見立てた金魚柄の染付の平茶碗。
茶入れは、蓋で隠れる部分にまで蒔絵の入った中継で、江戸期中期のもの。
主菓子は三友堂の渾身の創作菓子で、コシ餡に黒砂糖の香り豊かなゼリーが巻き付いて金星が鏤められている「星の雫」。
ヘタしたら、美術館に所蔵されてしまって、触ることもままならないような貴重なお道具が惜しげもなく披露された贅沢な贅沢な御席でした。
二席めは、記念館館長の永見会長が席主を務める桜製作所製の立礼机を用いた薄茶席(裏千家流)です。

本席の床には、「木の聲を聴け」と、ジョージナカシマ先生が常におっしゃっていた言葉を永見会長がそのまま心を込めて筆で書かれたという、味のある御軸がかかっていました。

水指、茶入(ウォールナット)、蓋置、茶杓(オリーブの木)、建水、菓子器がすべて桜製作所製の木製。

木の素敵さをこれでもかこれでもかと感じさせてくれるような、文字通り「木の聲が聴こえる」お茶席でした。

そして、お茶会終了後は、久しぶりの伏見塾に参加し、相変わらずの微に入り細に入りの面白い講義内容を久しぶりに堪能しました。
今日の講義は、待ち合いについて。各流派の踏み石の置き方や石の質、数、大小、にじり口からの距離、腰かけのこと、塵穴のことなどを詳しく教えて戴けました。
伏見先生の講義を生で聴けることは香川県で住んでいる人の特権ともいえるんだということが、昨日の二蝶での先生の米寿のお誕生会で改めて実感いたしまして、「また、万障繰り合わせて来なくちゃ」と再認識した次第です。次の講義は11日午前10時から。ご興味のある方は、ご一報ください。
そして、先生のご用意くださったお菓子も七夕に因んだ「天の川」でした。

好きな人と一年に一度しか逢えないなんて気の毒、、なんて言われることの多い彦星と織姫ですが、
たとえ一年に一度でも、大好きな人と丸一日、確実にデートできるなら、それはそれで羨ましい話。
やっとのことで約束に漕ぎ着けたとしても、その日確実に大好きな人に逢えるかどうかなんて、本当はわからないから。。
夏の始まりらしい一日が終わり、雨の香りがしてきました。
2009年07月04日
2008年10月19日
2008年08月12日
100t庵@牟礼の紹介ウェブ(中国語)

香川の魅力をアジアに発信中の
ヨッシーが,
石あかりロードの100t庵(50日間だけの,庵治石でできた石の茶室)
の魅力を,中国語で紹介してくれました。
http://www.sanuki-chaidays.jp/mure2.html
ちなみに,これは,茶室開きのときに,ヨッシーと一緒にお邪魔した「茶遊倶楽部(武者小路千家壮年部)」のお席です。
写真はそのときの「床」
今の家元のお筆の色紙がかかっているのは,アフリカの布
花入れは魚篭
etc..
ため息がでそうなお茶でした!
お忙しい隙間を縫っておつきあいいただいて,こちらこそありがとうございました♪
2008年03月24日
茶杓を削りました
 銘は
銘は海をみる
昨日は、永楽亭に茶杓削りに行ってきました。
同行は、伏見先生、学者Y氏、建築家A氏、御隠居文化人N氏、弁護人U氏などなど
講師は石州流千家十職の三原先生@奈良
伏見先生は、ゴマ竹とすす竹で、見事な茶杓を削り、銘を「夫婦仲睦まじく」とつけられていました。
帰りは、先生の戦争体験を根掘り葉掘り聞きながらのドライブでした。
2008年01月31日
獨楽庵茶会に行きませう
こんばんわ!
今日はさぬきネタじゃなくてすみません!!
素敵なご案内が届いていたことが判明しましたので、お知らせします。
ご興味を持たれる方がいらしたら、是非ご一緒しませんか?
とても急なのですが、締め切りは明日午前中ってことで、、ひとつ。。。
独楽庵茶会のご案内
日 時:2008年3月28日・29日 10時〜 11.30時〜 13時〜 14.30時〜 16時〜 のいずれか一席
場 所:獨楽庵(美ささ苑内) 八王子市元横山町
主 催:楽の会
濃茶席亭主:花井幸子(デザイナー)
薄茶席亭主:塚田晴可(ギャラリー「無境」オーナー)
楽の席亭主:桃山 樫崎家
点心席:美ささ苑
独楽庵について:
獨楽庵は千利休が天正年間に宇治田原に建てた二畳壁床の茶室がその起こりです。太い柱を特徴とするこの席は、一客一亭の究極の席と言われ、利久没後、尾形光琳と親しかった銀座内藏助が京都の屋敷に移築し、その後さらに浪速の豪商阿波屋が大阪に映し、さらにまた松平不昧公がそれを譲り受けて江戸の大崎に移築し愛用したと言われています。
幕末、ペリーの来航とともに国防上、急遽品川沖に砲台をつくることになり、大崎の茶苑もそのために取り壊されました。その際、松平家は「獨楽庵」を深川の下屋敷に移しましたが、翌年伊豆地震による大津波によって茶室は冠水してしまいました。しかし、大正十年、松平家からゆかりの品を譲り受けた武藤山治氏は、後に興福寺や法隆寺の古材を使って北鎌倉に「獨楽庵」を復元したのです。
終戦を迎えるとともに人心の荒廃の中でいちはやく茶の復活を求めて北鎌倉に「好日会」がつくられ、東西の数寄者たちの茶会の魁の舞台となりました。茶室は芝白金を経て、八王子に移築され、今に至ります。
todo消化状況
今日はさぬきネタじゃなくてすみません!!
素敵なご案内が届いていたことが判明しましたので、お知らせします。
ご興味を持たれる方がいらしたら、是非ご一緒しませんか?
とても急なのですが、締め切りは明日午前中ってことで、、ひとつ。。。
独楽庵茶会のご案内
日 時:2008年3月28日・29日 10時〜 11.30時〜 13時〜 14.30時〜 16時〜 のいずれか一席
場 所:獨楽庵(美ささ苑内) 八王子市元横山町
主 催:楽の会
濃茶席亭主:花井幸子(デザイナー)
薄茶席亭主:塚田晴可(ギャラリー「無境」オーナー)
楽の席亭主:桃山 樫崎家
点心席:美ささ苑
独楽庵について:
獨楽庵は千利休が天正年間に宇治田原に建てた二畳壁床の茶室がその起こりです。太い柱を特徴とするこの席は、一客一亭の究極の席と言われ、利久没後、尾形光琳と親しかった銀座内藏助が京都の屋敷に移築し、その後さらに浪速の豪商阿波屋が大阪に映し、さらにまた松平不昧公がそれを譲り受けて江戸の大崎に移築し愛用したと言われています。
幕末、ペリーの来航とともに国防上、急遽品川沖に砲台をつくることになり、大崎の茶苑もそのために取り壊されました。その際、松平家は「獨楽庵」を深川の下屋敷に移しましたが、翌年伊豆地震による大津波によって茶室は冠水してしまいました。しかし、大正十年、松平家からゆかりの品を譲り受けた武藤山治氏は、後に興福寺や法隆寺の古材を使って北鎌倉に「獨楽庵」を復元したのです。
終戦を迎えるとともに人心の荒廃の中でいちはやく茶の復活を求めて北鎌倉に「好日会」がつくられ、東西の数寄者たちの茶会の魁の舞台となりました。茶室は芝白金を経て、八王子に移築され、今に至ります。
todo消化状況


 芭蕉の葉っぱがテーブルクロス
芭蕉の葉っぱがテーブルクロス 瀬戸内海が借景の贅沢な席
瀬戸内海が借景の贅沢な席