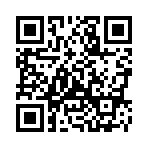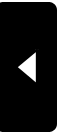2008年03月07日
今、「お寺」が地域の中でできること
先日のハカリゴト晩餐会のテーマの1つは、
「太古に建立されていまも現存するお寺は、今のお寺の機能とはまったく異なるいくつものシステムで成り立っていた。」
について。
それぞれの成り立ちは別として、今,お寺をどう活用するかは、場所の魅力をブラッシュアップする一つのキーワードだと感じていたので、今朝アップのるいままのブログに強く共鳴いたしまして。。。
てことで、
構想日本(JI)最新号のメールニュースから関連記事をコピペいたします。
八栗寺の本坊の屋根,うまげなよな~♪
*********************
【今、「お寺」が地域の中でできること 〜かけがえのない、“てらこや”をめざして〜】
生福寺 住職/泉州てらこや 主宰
石原 成昭
(泉大津青年会議所OB)
あなたにとってお寺はどんな存在ですか?
かつてお寺は大人にとっては信仰の場であり、交流の場でありました。
子どもにとっては遊びの場であり、学びの場でありました。その地域の人にとっては欠くことのできない、文字通り、心の拠り所でありました。
P・F・ドラッカーはその著書『非営利組織の経営』の中で、「いまも機能している最古の非営利機関は日本にある。奈良の古寺がそれである。創立の当初から、それらの寺は、非政府の存在であり、自治の存在だった」と述べています。お寺は地域のコミュニティの中心的な役割を担っていました。
NPOの先達でありました。
時代の流れによって、全てではありませんが、お寺は儀式を司るだけの、地域の人から遠い存在になってきたような気がします。時代に対応している、と言えば聞こえがいいのですが、実のところ本来の意義・目的を喪失し、時代に迎合しているのではないかと危惧をしていました。危機感を持っていました。しかしながら、何も出来ず手をこまねいている自分自身がいました。
数年前に鎌倉青年会議所が主体となって、大学生、地域のお寺や文化人、子、親と共に「鎌倉てらこや」という事業をはじめました。その事業は大きな成果を収め、昨年には5周年のシンポジュウムが開催され、多くの青年会議所がてらこや事業に取組むようになりました。いまでは、「てらこやネット」が立ち上げられ、相互協力が出来上がりつつあります。
私は昨年、泉大津青年会議所を卒業しました。現役のメンバーであるなら青年会議所のメンバーと共に事業を行なっていくのですが、私は青年会議所主体のてらこや事業ではなく、お寺からボランティアスタッフの皆様とともに、てらこやを行なっていこうと考えました。原点に立ち返るのです。
既に、多くのお寺や宗教者が、同じような取り組みを行なっておられることだと思います。
遅ればせながら、お寺から、まずは地域の子どもからお年寄り、全ての方に多種多様な、学びや気付きを発信することから始めます。このメールマガジンに登場される方は既にそれぞれの分野で大活躍されている方ばかりだと思っています。「これから何かを始めよう!」という者は皆無だと思っています。
この活動が机上の空論で終わることなく、絵に描いた餅で終わることなく、地域の皆様にとってお寺がかけがえのないものとなるべく、活動を行なっていきます。合掌
*石原 成昭(いしはら・なるあき)氏のプロフィール
1967年大阪生まれ。2006年度社団法人泉大津青年会議所理事長。
浄土宗総本山知恩院布教師。
「太古に建立されていまも現存するお寺は、今のお寺の機能とはまったく異なるいくつものシステムで成り立っていた。」
について。
それぞれの成り立ちは別として、今,お寺をどう活用するかは、場所の魅力をブラッシュアップする一つのキーワードだと感じていたので、今朝アップのるいままのブログに強く共鳴いたしまして。。。
てことで、
構想日本(JI)最新号のメールニュースから関連記事をコピペいたします。
八栗寺の本坊の屋根,うまげなよな~♪
*********************
【今、「お寺」が地域の中でできること 〜かけがえのない、“てらこや”をめざして〜】
生福寺 住職/泉州てらこや 主宰
石原 成昭
(泉大津青年会議所OB)
あなたにとってお寺はどんな存在ですか?
かつてお寺は大人にとっては信仰の場であり、交流の場でありました。
子どもにとっては遊びの場であり、学びの場でありました。その地域の人にとっては欠くことのできない、文字通り、心の拠り所でありました。
P・F・ドラッカーはその著書『非営利組織の経営』の中で、「いまも機能している最古の非営利機関は日本にある。奈良の古寺がそれである。創立の当初から、それらの寺は、非政府の存在であり、自治の存在だった」と述べています。お寺は地域のコミュニティの中心的な役割を担っていました。
NPOの先達でありました。
時代の流れによって、全てではありませんが、お寺は儀式を司るだけの、地域の人から遠い存在になってきたような気がします。時代に対応している、と言えば聞こえがいいのですが、実のところ本来の意義・目的を喪失し、時代に迎合しているのではないかと危惧をしていました。危機感を持っていました。しかしながら、何も出来ず手をこまねいている自分自身がいました。
数年前に鎌倉青年会議所が主体となって、大学生、地域のお寺や文化人、子、親と共に「鎌倉てらこや」という事業をはじめました。その事業は大きな成果を収め、昨年には5周年のシンポジュウムが開催され、多くの青年会議所がてらこや事業に取組むようになりました。いまでは、「てらこやネット」が立ち上げられ、相互協力が出来上がりつつあります。
私は昨年、泉大津青年会議所を卒業しました。現役のメンバーであるなら青年会議所のメンバーと共に事業を行なっていくのですが、私は青年会議所主体のてらこや事業ではなく、お寺からボランティアスタッフの皆様とともに、てらこやを行なっていこうと考えました。原点に立ち返るのです。
既に、多くのお寺や宗教者が、同じような取り組みを行なっておられることだと思います。
遅ればせながら、お寺から、まずは地域の子どもからお年寄り、全ての方に多種多様な、学びや気付きを発信することから始めます。このメールマガジンに登場される方は既にそれぞれの分野で大活躍されている方ばかりだと思っています。「これから何かを始めよう!」という者は皆無だと思っています。
この活動が机上の空論で終わることなく、絵に描いた餅で終わることなく、地域の皆様にとってお寺がかけがえのないものとなるべく、活動を行なっていきます。合掌
*石原 成昭(いしはら・なるあき)氏のプロフィール
1967年大阪生まれ。2006年度社団法人泉大津青年会議所理事長。
浄土宗総本山知恩院布教師。
Posted by マロンアルファー at 10:04│Comments(3)
│大事にするということ
この記事へのコメント
るいまま女史とマロン女史のブログを読んで、
日常の暮らしとお寺のかかわり方について考えさせられた。
40代を過ぎた頃から、
何かと法事、葬儀などに出かけることも多くなっていた昨年、
生まれ故郷の尾道から、香川にお墓を移した。
そのことで、少しの親戚以外、
生まれたまち「おのみち」とほとんど縁が切れたような気持ちになった。
お墓を移すということは、「お寺さん」を変えること。
香川町のお寺の中からあるお寺を紹介され、
そのご住職と何度か話をするうちに、
今まで知らなかった、この50才にもなるまで知らなかった
お寺と檀家、地域との繋がりに、
初めて気がついた。
今、ふたりのブログを読んで、その続きをとても楽しみにしています。
*******
私のかつての分野「舞台芸術・芸能」というジャンルで思い出したのは、
香川県民ホールがオープンしたばかりの頃の何かのイベントで、
お坊さんが唱えるお経を節をつけて唱え続ける「声明(しょうみょう)」を、
コーラスのように200人規模で県民ホールの大迫(オオゼリ)に載せた。
(これは私の演出制作ではありませんが)
リハーサルが終り、本番になった時に、なんと、大セリが上がらない!
あれこれ騒ぎがあり、結論としては・・・
「リハが終わった後に昼食お弁当を200人が食べてセリに乗ったために、
重量オーバーとなり、大セリの安全装置が作動し、止まった」
とのこと。(笑)
それから数年、オリーブホールでお坊さんのジャズバンドの演奏会や、
お寺でのライブなどが流行った。
今回ブログで紹介された方は、私がおつき合いしていたお坊さん世代の、
その次の若い世代でしょうか。
芸事だけでなく、まちと地域との関わりを模索する、
その動きに、期待、です。
日常の暮らしとお寺のかかわり方について考えさせられた。
40代を過ぎた頃から、
何かと法事、葬儀などに出かけることも多くなっていた昨年、
生まれ故郷の尾道から、香川にお墓を移した。
そのことで、少しの親戚以外、
生まれたまち「おのみち」とほとんど縁が切れたような気持ちになった。
お墓を移すということは、「お寺さん」を変えること。
香川町のお寺の中からあるお寺を紹介され、
そのご住職と何度か話をするうちに、
今まで知らなかった、この50才にもなるまで知らなかった
お寺と檀家、地域との繋がりに、
初めて気がついた。
今、ふたりのブログを読んで、その続きをとても楽しみにしています。
*******
私のかつての分野「舞台芸術・芸能」というジャンルで思い出したのは、
香川県民ホールがオープンしたばかりの頃の何かのイベントで、
お坊さんが唱えるお経を節をつけて唱え続ける「声明(しょうみょう)」を、
コーラスのように200人規模で県民ホールの大迫(オオゼリ)に載せた。
(これは私の演出制作ではありませんが)
リハーサルが終り、本番になった時に、なんと、大セリが上がらない!
あれこれ騒ぎがあり、結論としては・・・
「リハが終わった後に昼食お弁当を200人が食べてセリに乗ったために、
重量オーバーとなり、大セリの安全装置が作動し、止まった」
とのこと。(笑)
それから数年、オリーブホールでお坊さんのジャズバンドの演奏会や、
お寺でのライブなどが流行った。
今回ブログで紹介された方は、私がおつき合いしていたお坊さん世代の、
その次の若い世代でしょうか。
芸事だけでなく、まちと地域との関わりを模索する、
その動きに、期待、です。
Posted by rookie@仕事中 at 2008年03月07日 15:35
rookie>
彼らと10年は違わない世代ですね。
というか、広まりをみせてきたというほうがいいかもです。
牟礼の洲崎寺さんのあと、仏生山の円光寺さんにも、境内の開放をお願いして、地元の人たちが集えるものを、地元のひとたちで作ってもらえるように道をつけましたが
すぐに動いていただける40代にのるかのらずかくらいの若い住職と、それを支える、ものわかりのいいおじいちゃん住職という形が 良い形ですすむような気がします。
寺は、集いの場でもあったけれど、歴史の中では、寺ごとの役割も違っていて、その誇りは決してつぶさぬように、いろいろ仕掛けていくことが大事だなと
私は思っております。
彼らと10年は違わない世代ですね。
というか、広まりをみせてきたというほうがいいかもです。
牟礼の洲崎寺さんのあと、仏生山の円光寺さんにも、境内の開放をお願いして、地元の人たちが集えるものを、地元のひとたちで作ってもらえるように道をつけましたが
すぐに動いていただける40代にのるかのらずかくらいの若い住職と、それを支える、ものわかりのいいおじいちゃん住職という形が 良い形ですすむような気がします。
寺は、集いの場でもあったけれど、歴史の中では、寺ごとの役割も違っていて、その誇りは決してつぶさぬように、いろいろ仕掛けていくことが大事だなと
私は思っております。
Posted by るいまま at 2008年03月08日 13:11
at 2008年03月08日 13:11
 at 2008年03月08日 13:11
at 2008年03月08日 13:11ルーキーさま
お墓を移すことは、他人が考えている以上に大変な作業なのでしょうね。自分の父のお墓を移す事を考えたとき想像ができました。
とにもかくにも、高松への永住(予定)ありがとうございます。
父の恋人の一人が大きなお寺の尼さんだったこと、還暦の時に得度したこと、その尼さんの仲人でお寺の息子とお見合いさせられたこと、など私の人生では断片的にお寺との関わりはありますが、その程度のものでした。今、静かな速度であるお寺との関わりが深くなろうとしています。流れに身を任せつつも、何を求められているのか、それに応える事ができるのか、を見極めている最中。
JIフォーラムの参加記もアップしますね♪
るいまま>
寺が10軒あればその歴史や役割も10色ありそうですね。
「誇りをつぶさぬように」
これ大事ですね
お墓を移すことは、他人が考えている以上に大変な作業なのでしょうね。自分の父のお墓を移す事を考えたとき想像ができました。
とにもかくにも、高松への永住(予定)ありがとうございます。
父の恋人の一人が大きなお寺の尼さんだったこと、還暦の時に得度したこと、その尼さんの仲人でお寺の息子とお見合いさせられたこと、など私の人生では断片的にお寺との関わりはありますが、その程度のものでした。今、静かな速度であるお寺との関わりが深くなろうとしています。流れに身を任せつつも、何を求められているのか、それに応える事ができるのか、を見極めている最中。
JIフォーラムの参加記もアップしますね♪
るいまま>
寺が10軒あればその歴史や役割も10色ありそうですね。
「誇りをつぶさぬように」
これ大事ですね
Posted by マロン at 2008年03月08日 19:56
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。