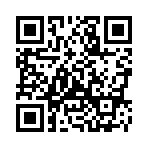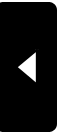2011年04月03日
いろいろ選挙考
昨夜、某夜ゼミにて、応援している政治家のチラシを配り、構想を代理で語るという身の知らずなことをしてみました。
そこは、香川県の「文化人」「哲学者」「評論家」「政治家」「学者」など、錚々たる人々の集まりでした。
その方がなぜ地元ではなく別のところから立候補したかという質問をいただいたので、「理想選挙」という考え方について、受け売りで語ったところ、つっこまれて、血だらけに。。
さらに、「ポスターの顔がガラが悪い。もう少しやわらかい表情じゃないと、入れたいと思わない」と、会場にいた二人の論客にも言われてしまいました。
個人的には、腹は真っ黒なのに笑顔だけまっ白な笑顔のポスターって見てて気持ちが悪いけど、それに比べてなんて凛々しいんだろう、(むしろ本人よりも素敵にできてる!)と惚れ惚れしていたので、そのショックたるや。。
それでも気を取り直して、
「もうそろそろ、ポスターの表情や、イメージだけで選挙するのはやめませんか?」というと、
「それを屁理屈というんだよ」と怒られて、散々。
まだまだここでは(きっと日本全国でも)理想選挙も、強面のポスターも、市民権が得られていないのが現状のようです。
たとえば、田中康夫、たとえば鳩山由紀夫は、自分の地元ではないところから立候補をしていますが、これが理想選挙のひとつです。議員が「地域の利益代表にはならない形」を理想選挙というそうです。
地元から出ている立候補した人が当選したら、「じゃあ、うちの近くのこの道を広くしてもらえる」等、地元に利益を還元することが、暗黙のうちに求められますが、本来議会の議員の役割は、予算をできるだけたくさん分捕って、地元に還元して「私ががんばりました」ということなんじゃなかったんじゃないでしょうか。
みんながそれをしていたら、議会はただの予算の各地元への分捕り合戦となってしまい、その県なり、市なりで、みんなで議論してルールや方向を考えて決めなければならないことは、二の次にならないだろうか。
実は、長く、そんな疑問を持っていたのですが、「理想選挙」という抽象的な名前の言葉の意味を教えられて、長年の疑問が払しょくされました。
それから、いまだに日本では、候補者によるネットでの選挙運動は禁じられています。この見解については、近年微妙に意見がわかれていたりもしているようですが、有権者が、できるだけ多くの候補者の情報を得るのには、双方ともに使えるツールはどんどん使うのが本来だと思うのですが、いまだに禁止という理由が、考えつきません。
ネット選挙に関する考え方:参考
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E9%81%B8%E6%8C%99
http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20100628/215161/
本来の議会のあるべき姿(これがきちんとなされていたら、そもそも「事業仕訳」などという手法が脚光を浴びることはなかったですね)、議員の本来の役割、そして、自分たちが代表を選ぶ基準、選んだあとのチェックの仕方、、そして、本来あるべき選挙の姿ってどんなんだろう。
縁があって、生まれて初めて選挙の手伝いを始めたことから、これまで考えたこともなかったこと、考えてみたけど結論がでなかったことを、改めて考える貴重な機会を与えられております。
政治は生活、人生と直結している。
若者よ、投票所に行こう。

そこは、香川県の「文化人」「哲学者」「評論家」「政治家」「学者」など、錚々たる人々の集まりでした。
その方がなぜ地元ではなく別のところから立候補したかという質問をいただいたので、「理想選挙」という考え方について、受け売りで語ったところ、つっこまれて、血だらけに。。
さらに、「ポスターの顔がガラが悪い。もう少しやわらかい表情じゃないと、入れたいと思わない」と、会場にいた二人の論客にも言われてしまいました。
個人的には、腹は真っ黒なのに笑顔だけまっ白な笑顔のポスターって見てて気持ちが悪いけど、それに比べてなんて凛々しいんだろう、(むしろ本人よりも素敵にできてる!)と惚れ惚れしていたので、そのショックたるや。。
それでも気を取り直して、
「もうそろそろ、ポスターの表情や、イメージだけで選挙するのはやめませんか?」というと、
「それを屁理屈というんだよ」と怒られて、散々。
まだまだここでは(きっと日本全国でも)理想選挙も、強面のポスターも、市民権が得られていないのが現状のようです。
たとえば、田中康夫、たとえば鳩山由紀夫は、自分の地元ではないところから立候補をしていますが、これが理想選挙のひとつです。議員が「地域の利益代表にはならない形」を理想選挙というそうです。
地元から出ている立候補した人が当選したら、「じゃあ、うちの近くのこの道を広くしてもらえる」等、地元に利益を還元することが、暗黙のうちに求められますが、本来議会の議員の役割は、予算をできるだけたくさん分捕って、地元に還元して「私ががんばりました」ということなんじゃなかったんじゃないでしょうか。
みんながそれをしていたら、議会はただの予算の各地元への分捕り合戦となってしまい、その県なり、市なりで、みんなで議論してルールや方向を考えて決めなければならないことは、二の次にならないだろうか。
実は、長く、そんな疑問を持っていたのですが、「理想選挙」という抽象的な名前の言葉の意味を教えられて、長年の疑問が払しょくされました。
それから、いまだに日本では、候補者によるネットでの選挙運動は禁じられています。この見解については、近年微妙に意見がわかれていたりもしているようですが、有権者が、できるだけ多くの候補者の情報を得るのには、双方ともに使えるツールはどんどん使うのが本来だと思うのですが、いまだに禁止という理由が、考えつきません。
ネット選挙に関する考え方:参考
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E9%81%B8%E6%8C%99
http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20100628/215161/
本来の議会のあるべき姿(これがきちんとなされていたら、そもそも「事業仕訳」などという手法が脚光を浴びることはなかったですね)、議員の本来の役割、そして、自分たちが代表を選ぶ基準、選んだあとのチェックの仕方、、そして、本来あるべき選挙の姿ってどんなんだろう。
縁があって、生まれて初めて選挙の手伝いを始めたことから、これまで考えたこともなかったこと、考えてみたけど結論がでなかったことを、改めて考える貴重な機会を与えられております。
政治は生活、人生と直結している。
若者よ、投票所に行こう。
Posted by マロンアルファー at 22:33│Comments(0)
│政治は生活
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。