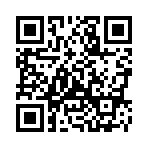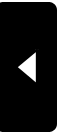2008年01月16日
たんぽぽ茶人 (世界へ発信したいsanuki人 #1)
お名前:伏見 章先生
キーワード:茶の湯、茶文化、牟礼、柴犬
種別:凄い人・愛すべき人
お住まい:牟礼町
紹介文:
御歳87歳の伏見家四代目の偉大で可憐な茶人。
数寄者でもあった先祖代々よりから受け継いだ膨大な量の価値ある茶道具と茶室(恕庵)を家屋敷ごと牟礼町(合併前の)に寄贈し、現在は夫人とともに恕庵文庫の管理に務める。
先代には表千家流の人もいらしたらしいが、伏見先生は裏千家流を極め、現在は天衣無縫流を実践する。
天衣無縫流とは、時代に合っていない形骸化した茶の湯のルールを軌道修正し、「心から人をもてなすために必要なこと、不必要なこと」を何をも恐れず取捨選択した流儀。具体例として、正客のための「煙草盆(キセル煙草のための道具)」を廃止するなど。しかしこれらはあくまでも人を大切に扱うための基本を押さえた上での勇気ある軌道修正である。考えてみると千利休を始めとした歴史上の数々の茶人は、その作法を時代に合ったものに「勇気をもって」変えてきた。現代人は変えることを極度に恐れる傾向にあるらしい。
季節の茶事などに先生にお供することができたときには、もてなしてくれる人の愛情をどのような立ち居振る舞いや言葉で返すべきなのかを、多くを語られることなくそのお姿でもって教わることができる。
現職時代は、中学の理科の先生として教壇にたっていらしたためか、講義が上手く面白い。念入りに隠された茶文化史の裏の裏まで知り尽くす知識の深さを、その質の高い講義テクニックで巧みに噛み砕き、惜しげもなく披露・還元する講座「伏見塾」を2006年1月に開講された。会場である恕庵は、すでに実施されていた南方録講義とともに、あらゆる意味で聖地となっている。
余談となるが、開講時より中村晄三氏、石田雄士氏ら(のちにDBにてご紹介予定)熱心な塾生により記録し続けられている「伏見塾講義ノート」は50回めに迫る。講義は伏見先生の口から発せられる格調高いさぬき弁を味わうことに醍醐味があるが、講義ノートは彼ら熱心な塾生が、先生のおっしゃったキーワードをさらにフカホリして研究しネットなどで得た画像や詳細情報を満載して編纂されているため、後世に残る文書となることはほぼ間違いないであろう。
以上のように、伏見章先生は、広域にて右にでる人のいないほどの偉大な茶人でありながら、そのお人柄はたんぽぽのように暖かで優しくて素朴ですらある。(以前は菜の花と例えていたが、菜の花は千利休に纏る別の意味を持つ花なのでたんぽぽと改正した)。すでに初代の社中陣は結婚などで全国に散らばり、彼女ら自身も孫弟子までかかえる茶人と成長している模様であり、いわば先生は天皇または仙人と恐れられるべき人。しかし現在も、そのたんぽぽなお人柄を慕って20代30代の社中志願者が後を絶たない。
伏見先生の愛するものに、柴犬がある。最多時には8匹、普段は6匹柴犬を飼っていらしたとのこと。犬のためのアパートが今も庭の片隅にひっそりと佇んでいる。恕庵文庫の隅の方に、先生愛蔵の「犬のアルバム」が大切に保管されている。表紙を開くと、犬に顔をなめられて相好を崩す、少し若い頃の先生に会うことができる。先生の洋服には時々、ダックスフンドやセントバーナードの刺繍やプリントの入ったものが見受けられるが、夫人談によると「柴犬のモチーフのものがないから、洋犬で我慢しているの」とのこと。
今は一匹も買っていない理由は「犬より早よ死ぬんがかわいそな」からとのこと。大切に保管されている犬のアパートを見ると、その気持ちが忍ばれて胸から熱いものが込み上げてくる。
以上、牟礼の伏見先生は、その茶文化の見識の深さ、お人柄、言動の清らかさから、最初に世界に発信したい香川の魅力的な方と勝手に判断して、ご紹介しました。(文責:マロン)

キーワード:茶の湯、茶文化、牟礼、柴犬
種別:凄い人・愛すべき人
お住まい:牟礼町
紹介文:
御歳87歳の伏見家四代目の偉大で可憐な茶人。
数寄者でもあった先祖代々よりから受け継いだ膨大な量の価値ある茶道具と茶室(恕庵)を家屋敷ごと牟礼町(合併前の)に寄贈し、現在は夫人とともに恕庵文庫の管理に務める。
先代には表千家流の人もいらしたらしいが、伏見先生は裏千家流を極め、現在は天衣無縫流を実践する。
天衣無縫流とは、時代に合っていない形骸化した茶の湯のルールを軌道修正し、「心から人をもてなすために必要なこと、不必要なこと」を何をも恐れず取捨選択した流儀。具体例として、正客のための「煙草盆(キセル煙草のための道具)」を廃止するなど。しかしこれらはあくまでも人を大切に扱うための基本を押さえた上での勇気ある軌道修正である。考えてみると千利休を始めとした歴史上の数々の茶人は、その作法を時代に合ったものに「勇気をもって」変えてきた。現代人は変えることを極度に恐れる傾向にあるらしい。
季節の茶事などに先生にお供することができたときには、もてなしてくれる人の愛情をどのような立ち居振る舞いや言葉で返すべきなのかを、多くを語られることなくそのお姿でもって教わることができる。
現職時代は、中学の理科の先生として教壇にたっていらしたためか、講義が上手く面白い。念入りに隠された茶文化史の裏の裏まで知り尽くす知識の深さを、その質の高い講義テクニックで巧みに噛み砕き、惜しげもなく披露・還元する講座「伏見塾」を2006年1月に開講された。会場である恕庵は、すでに実施されていた南方録講義とともに、あらゆる意味で聖地となっている。
余談となるが、開講時より中村晄三氏、石田雄士氏ら(のちにDBにてご紹介予定)熱心な塾生により記録し続けられている「伏見塾講義ノート」は50回めに迫る。講義は伏見先生の口から発せられる格調高いさぬき弁を味わうことに醍醐味があるが、講義ノートは彼ら熱心な塾生が、先生のおっしゃったキーワードをさらにフカホリして研究しネットなどで得た画像や詳細情報を満載して編纂されているため、後世に残る文書となることはほぼ間違いないであろう。
以上のように、伏見章先生は、広域にて右にでる人のいないほどの偉大な茶人でありながら、そのお人柄はたんぽぽのように暖かで優しくて素朴ですらある。(以前は菜の花と例えていたが、菜の花は千利休に纏る別の意味を持つ花なのでたんぽぽと改正した)。すでに初代の社中陣は結婚などで全国に散らばり、彼女ら自身も孫弟子までかかえる茶人と成長している模様であり、いわば先生は天皇または仙人と恐れられるべき人。しかし現在も、そのたんぽぽなお人柄を慕って20代30代の社中志願者が後を絶たない。
伏見先生の愛するものに、柴犬がある。最多時には8匹、普段は6匹柴犬を飼っていらしたとのこと。犬のためのアパートが今も庭の片隅にひっそりと佇んでいる。恕庵文庫の隅の方に、先生愛蔵の「犬のアルバム」が大切に保管されている。表紙を開くと、犬に顔をなめられて相好を崩す、少し若い頃の先生に会うことができる。先生の洋服には時々、ダックスフンドやセントバーナードの刺繍やプリントの入ったものが見受けられるが、夫人談によると「柴犬のモチーフのものがないから、洋犬で我慢しているの」とのこと。
今は一匹も買っていない理由は「犬より早よ死ぬんがかわいそな」からとのこと。大切に保管されている犬のアパートを見ると、その気持ちが忍ばれて胸から熱いものが込み上げてくる。
以上、牟礼の伏見先生は、その茶文化の見識の深さ、お人柄、言動の清らかさから、最初に世界に発信したい香川の魅力的な方と勝手に判断して、ご紹介しました。(文責:マロン)
Posted by マロンアルファー at 20:27│Comments(2)
│世界へ発信したい人DB
この記事へのコメント
こんにちは♪
伏見先生の写真・・・あります。取材させていただいたときのやけど・・・
でも、もうちゃんとアップしてますからいいかなっ・・・
伏見先生の写真・・・あります。取材させていただいたときのやけど・・・
でも、もうちゃんとアップしてますからいいかなっ・・・
Posted by ももいろどんぐり at 2008年01月16日 23:18
at 2008年01月16日 23:18
 at 2008年01月16日 23:18
at 2008年01月16日 23:18ももどん、ありがとう!!
どっちにしてもほすぃ〜です!
本文に複数貼れるはずなんで♪
どっちにしてもほすぃ〜です!
本文に複数貼れるはずなんで♪
Posted by マロンアルファー at 2008年01月16日 23:24
at 2008年01月16日 23:24
 at 2008年01月16日 23:24
at 2008年01月16日 23:24※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。